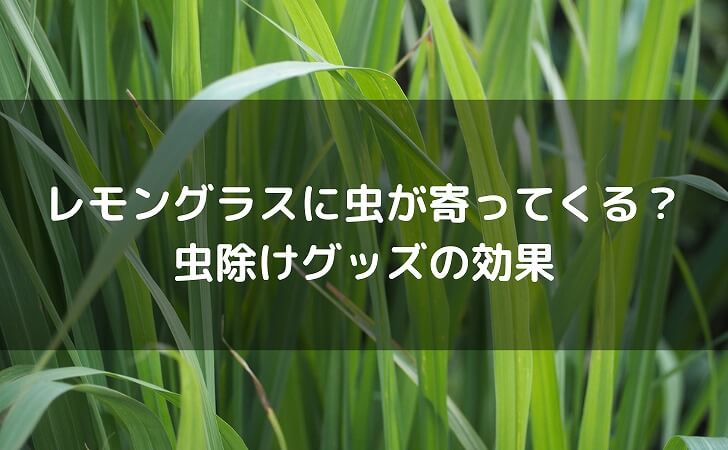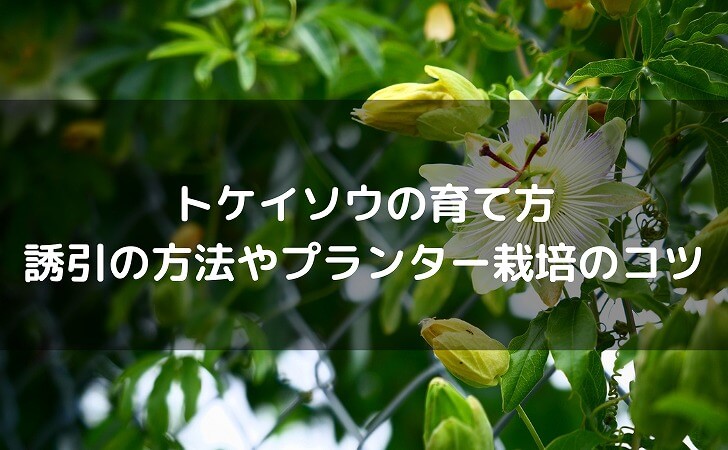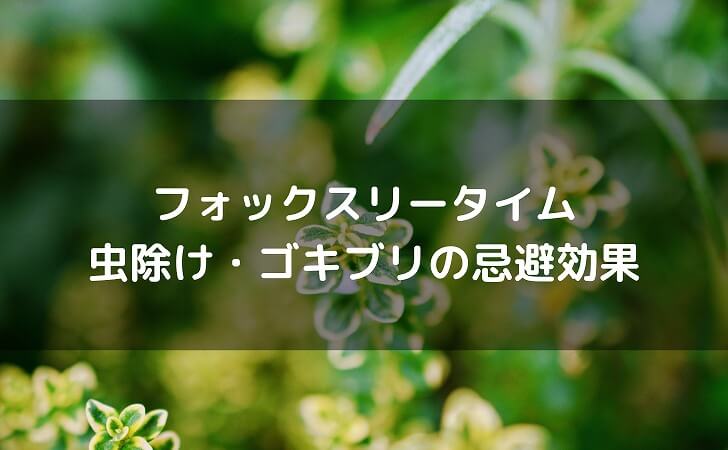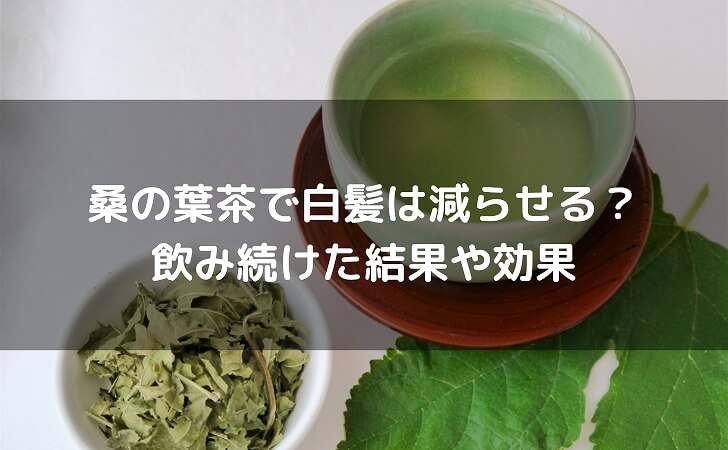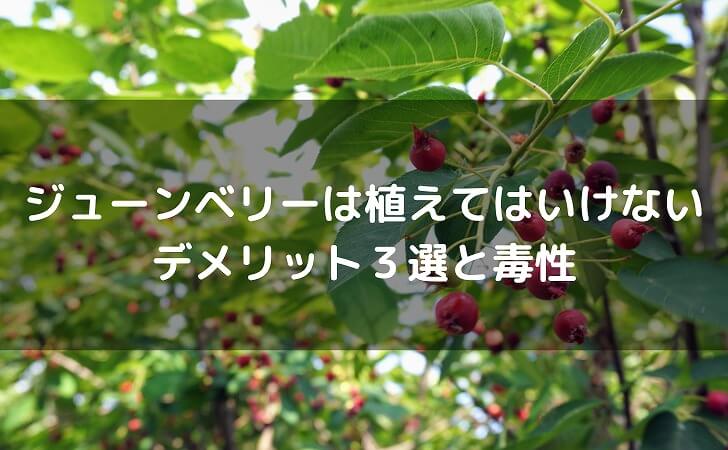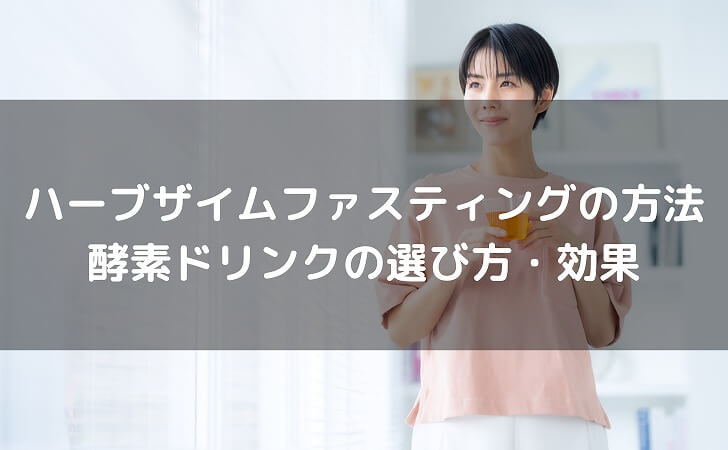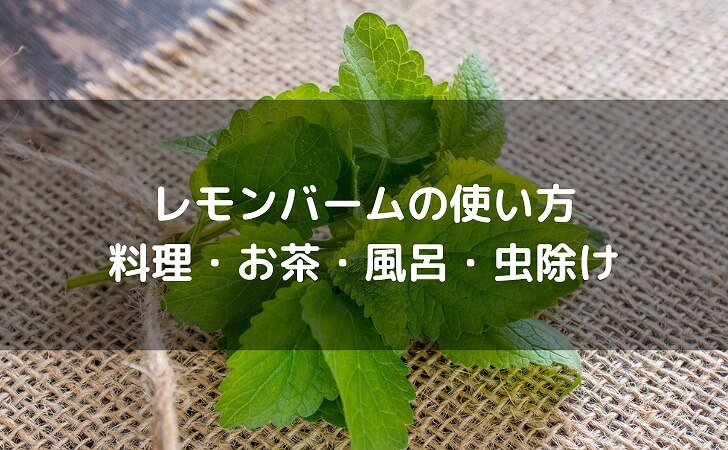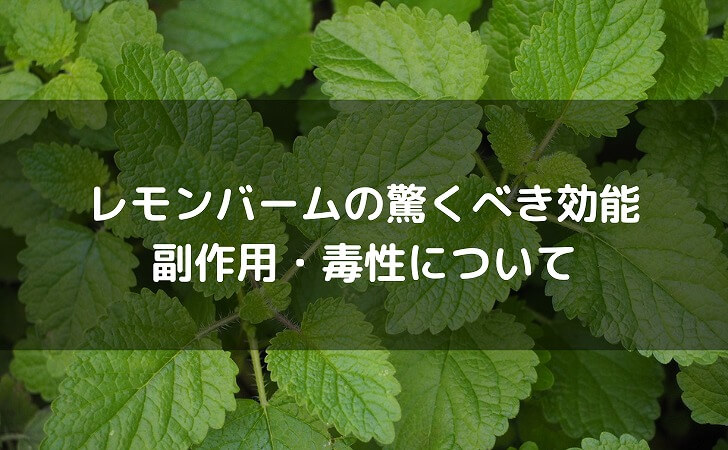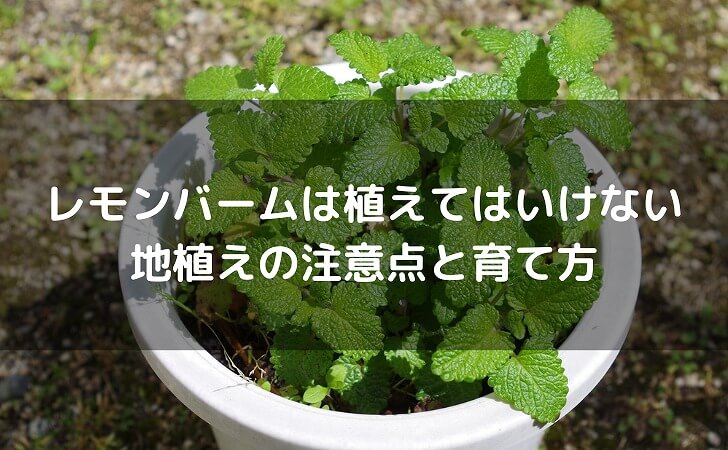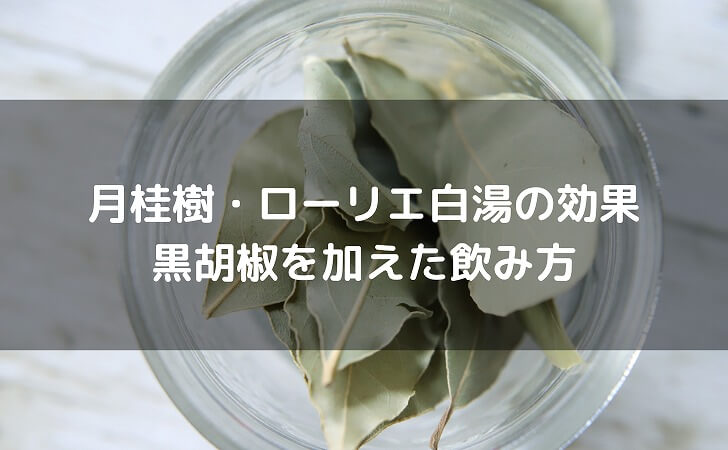トケイソウを育てる際には、適切な冬越しや誘引の方法が必要不可欠です。
基本的な環境づくりと、誘引や剪定のほか、プランターで育てる際のコツについてお伝えします。
この記事では、トケイソウのプランター栽培のコツをはじめ、冬の厳しい寒さから守り、一年中健やかに育てるための秘訣をご紹介します。
トケイソウ栽培に適した環境づくり
トケイソウは日当たりのよい環境を好みます。
トケイソウの種類によって異なりますが、一般的な生育適温が20〜30℃です。耐寒性のない品種も多く存在するので育てる際に耐寒性の有無について確認してください 。
基本的な環境づくりとして、用土づくりと水・肥料の与え方について次の項でお伝えします。
用土づくり
トケイソウは水はけの良い用土を好む植物です。
市販の果樹用培養土や草花用培養土を使うことができますが、赤玉土や腐葉土、日向土などを混ぜて水はけと通気性を高めるとより良いでしょう。
用土の配合例の目安としては、赤玉土(小粒)5:腐葉土3:日向土2の割合で混ぜることで栽培に適した用土が作れます。
そのほか、培養土にパーライトやバーミキュライトなどの軽石を2割ほど混ぜることでも適した用土にすることができます。
これらの方法によって、トケイソウの根に空気と水分を適度に供給できる状態を保てるようになります。
水やり
トケイソウは、水をやりすぎると根腐れや枯れの原因になるので過度な水やりは禁物です。
地植えの場合は、基本的には降雨による水のみで充分なので、水やりを気にする必要はありません。(夏に降雨がない日が何日も続く場合は朝か晩に水やりは必要となります)
鉢植えの場合は、土の表面が乾いたらしっかりと水を与えます。日当たりのいい場所で育てたい植物なので、夏の昼間には水やりをせずに、気温が下がる朝か夕方にしましょう。
なお、冬の間はそれほど水がいらないので、寒くなったら水やりは様子をみながら少なめにしましょう。
肥料の与え方
4月から10月頃までは、毎月1回程度の頻度で窒素成分の少ない緩効性の固形肥料を与えます。窒素肥料が多すぎると茎葉だけ茂り、花つきが悪くなってしまうのでご注意ください。
冬場は特に肥料を与える必要はありません。
トケイソウの種まき時期と方法
トケイソウの種まきに適した時期は、春から初夏の5月から6月頃です 。この時期は気温が高く、発芽に適しています。冬に種まきをすると発芽率が低くなるので、避けましょう。
トケイソウの種まきの手順は次のとおりです。
- 土を平らにし、表面に6粒ほど均等に種をまく。
- 種に薄く覆土をする。(覆土は1mm程度で充分です)
- 霧吹きなどで土全体が湿るように水やりをする。
- 土が乾燥しないように毎日水やりをする。
- 芽後2週間ほどで本葉が出たら間引きする。
種は小さいので、ピンセットなどで扱うと便利です。トケイソウの種は発芽しにくいので覆土は薄くして温度と湿度を保つことがポイントです。
ポットや鉢に種まきをする場合は、発芽までの場所は室内の明るいところで、温度を確保するために鉢ごとビニール袋に入れておくと良いです。ビニール袋には穴をあけて通気性を良くすると良いでしょう。
発芽温度は20~25℃程度が適しているので、適度に調整して発芽しやすい環境づくりをつくるようにします。
本葉が4枚ほど出たら、5号ポットなど大きめの鉢に植え替えます。植え替えの方法は次の項で詳しくお伝えします。
トケイソウの植え替え時期と方法
トケイソウの植え替えに適した時期は、春から初夏の4月から6月頃です。この時期は気温が高く根付きやすいです。
鉢植えの場合は、根詰まりを防ぐために1~2年に1回、1回り大きな鉢に植え替えると良いでしょう。
トケイソウの植え替えは以下のとおり行います。
- 新しい鉢と土を用意する。
- 苗を取り出す。
- 根が詰まっていたら、根鉢をくずして古い根などを切り取る。
- 新しい鉢に土を入れて平らにして苗を入れる。
- 根元が浅くなっていないか確認する。
- 土を戻して固めた後、たっぷりと水やりをする。
- 支柱を立てる
トケイソウはツル性の植物なので支柱やフェンス、オベリスクなどに誘引する必要があります。早めに支柱や誘引用のネットなどを設置し、つるが巻きつくようにしておきましょう。
トケイソウの地植えの時期と方法
トケイソウの地植えに適した時期は、春から初夏の4月から6月頃です 。この時期は気温が高く、根付きやすいです。
トケイソウの地植えの手順は次のとおりです。
- 植え付ける場所に苗の根鉢よりも一回り大きな穴を掘る。
- 穴の深さは根鉢と同じくらいにする。
- 苗をポットから取り出して穴に入れる。
- 根元が浅くならないように土を戻して固める。
- たっぷりと水やりをする。
- 支柱を立てる。
地植えの場合も、早めに支柱や誘引用のネットなどを設置し、つるが巻きつくようにしておきましょう。
トケイソウを鉢植え・プランターで育てる方法
鉢やプランターの大きさは、株の大きさに合わせて選びます。一般的には、根鉢の直径よりも2~3cm程度大きいものが適しています。
小さすぎると根詰まりを起こしやすく、大きすぎると水分が蒸発しにくくなるので適度な大きさを選ぶようにします。
鉢やプランターの形は、深さよりも幅の広いものがおすすめです。トケイソウは浅根性なので、深さがあると土が乾きにくくなります。また、幅が広いと株が広がって花が多く咲きます。
栽培に適した環境づくりの項でも書きましたが、土は水はけを良くして、土が乾いたらしっかりと水を与えます。過湿にすると根腐れや立ち枯れの原因になるのでご注意ください。
肥料は春から秋の成長期に月に1回程度、緩効性の化成肥料や有機質肥料を規定量施します。
トケイソウの室内での育て方のポイント
基本的な育て方としては、前項の鉢植え・プランターで育てる方法をご参照ください。
室内で育てる際のポイントとしては、日当たりと風通しの良い場所に置くことが挙げられます。
冬は室内の窓際などで管理しますが、直射日光が当たりすぎると葉が焼けるので、カーテンなどで調節します。夏は室内が暑くなりすぎないように、エアコンや扇風機などで温度と湿度を適切に保ちましょう。
トケイソウの花が咲く時期と香り・花言葉
トケイソウの花が咲く時期は種類によっても異なりますが、春から秋の5月から10月頃です。
トケイソウの花は一日花で、朝に開花して日暮れとともにしぼんでしまいます。しかし、花付きが良く、夏の間は毎日のように花を楽しめます。特にトケイソウの花が見頃を迎えるのは7月~8月です。
トケイソウの花には香りがありますが、品種によって異なります。一般的には甘い香りやフルーティーな香りがすると言われていますが、中には臭いと感じる人もいるようです 。
トケイソウの花言葉は、「聖なる愛」「信仰」「宗教的熱情」「情熱的に生きる」などです 。これらの花言葉は、トケイソウの花の特徴がキリストの受難を象徴するとされることからきています。
例えば、先端が3つに分岐しためしべはキリストを貼り付けにした釘、花の内側に広がる糸のような副花冠は茨の冠、10数枚の花びらは弟子たち、つるはキリストを打った鞭などとなぞらえられています 。
トケイソウを摘心・剪定・芽かきする方法と目的・時期
トケイソウを育てるうえで摘心・剪定・芽かきは必要です。それぞれの方法と目的・時期について以下にまとめました。
| 摘心 |
トケイソウの摘心は、植物の成長を横方向に促し、枝分かれや花付きを良くすることを目的とします。手でひねって摘み取るか、ハサミでカットするかのいずれかの方法で行います。適した時期は、育てる品種や開花期によって異なりますが、主に発育のよい生育期に行います。 |
| 剪定 |
トケイソウの剪定は、植物の形を整えたり、枯れたり病気になったりした部分を除去したりすることを目的とします。ハサミや剪定ばさみを使ってカットしていきます。適した時期は品種や開花期によって異なりますが、一般的には春か秋に行います。 |
| 芽かき |
トケイソウの芽かきは、植物の栄養を本来の花や果実に集中させたり、風通しや日当たりを良くしたりすることを目的とします。手でつまんで抜くか、ハサミでカットしていきます。適した時期は品種や開花期によって異なりますが、主に生育期に行います。 |
トケイソウの耐寒性と冬越しの方法
トケイソウの耐寒性は、品種によって異なります。一般的には、関東地方よりも西の温暖な地方で地植えに向いていますが、それ以外の地域では鉢植えにして冬越しするか、耐寒性の高い品種を選ぶのが望ましいです 。
なお、耐寒性の高い品種としては、以下のようなものがあります 。
| カエルレア |
15℃までの寒さに耐えることができます。ある程度霜に当たって葉が落ちても翌年にはまた葉や花がつきます。 |
| クリア・スカイ |
-10℃までの寒さに耐えることができます。青白い花を咲かせます。 |
| コンスタンス・エリオット |
-5℃までの寒さに耐えることができます。白い花を咲かせます。 |
トケイソウの冬越しの方法は鉢植えと地植えで異なります。それぞれの方法は次のとおりです。
| 鉢植え |
10月頃から室内や温室などに移動して管理します。日光が当たる場所に置き、水やりは控えめにします。気温が低くなると葉が落ちることがありますが、春になれば新芽が出てきます。 |
| 地植え |
耐寒性の高い品種であれば、株元をワラや落ち葉などで覆って保温することで冬越しできます 。また、株全体に不織布をかぶせたり、敷きわらを敷くなどの防寒対策を行えば、さらに冬越しに成功する可能性が高くなります。 |
トケイソウは北海道でも越冬できるのか
トケイソウは北海道でも越冬できる可能性がありますが、以下の点に注意する必要があります。
| 品種の選択 |
トケイソウは品種によって耐寒性が異なるので、北海道で越冬させる場合は、耐寒性の高い品種を選ぶことが重要です。カエルレアやクリア・スカイ、コンスタンス・エリオットなどがおすすめです。 |
| 鉢植えで育てる |
北海道であれば地植えで冬越しするのは難しく、鉢植えで育てて室内で冬越しするようにしましょう。 |
| 気温の変化に注意する |
トケイソウは急激な気温の変化に弱いので、冬越しする場合は、気温の変化に注意して管理することが必要です。特に、春先に暖かくなってから急に冷え込むような場合は、株が凍傷を起こす可能性があります。 |
トケイソウの誘引の目的と方法
トケイソウはツル性の植物で、支柱やフェンス、オベリスクなどに巻きつかせて育てることが一般的です。誘引することで、美しいつるや花を広げ、視覚的な効果を高めます。
誘引の方法は次のとおりです。
- しっかりと支柱やフェンスに絡ませる。
- 新たに伸びてきたつるを四方に広がるように導く。
- 手が届く低い位置では、できるだけ横方向に誘引してわき芽の発生を促す。
なお、成長期はつるがよく伸びてつる同士が絡み合ってしまうため、1~2週間に1回、つるの誘引を行い、伸びすぎた枝は切り戻しをします。
トケイソウの増やし方
トケイソウは種まきのほか、挿し木と株分けによって増やすことができます。
ここでは、
この2つの方法についてご紹介します。
挿し木で増やす方法と時期
トケイソウの挿し木は、5月~7月が適期です。挿し木で増やす方法は次のとおりです。
1.挿し穂を切る
色が濃い節を選び、2~3節の長さにカットします。ツルを切り落とし、葉も半分切り落とします。
2.水揚げする
切った挿し穂の根元を数時間水につけて水揚げします。これは切り口から水分が抜けるのを防ぐためです。
3.用土を用意する
挿し木には、水はけの良い用土を用います。市販の培養土や赤玉土と腐葉土を混ぜたものが適しています。
4.挿し穂を挿す
用土に穴をあけて、挿し穂の下1/3程度を挿します。土を軽く押さえて固定します。
5.水やりをする
挿し穂を挿したら、霧吹きなどで水やりをします。水やりは乾燥しない程度に行います。水やり過ぎると根腐れの原因になります。
6.根付かせる
水やりをしたら、ビニール袋などで覆って温室状態にします。日光が当たる場所に置きますが、直射日光は避けましょう。気温は20~25℃程度が適しています。根付くまでに約1~2ヶ月かかります。
株分けで増やす方法と時期
トケイソウの株分けは、春から夏にかけて行うことができます 。株分けで増やす方法は次のとおりです。
1.株を掘り出す
トケイソウの株を鉢から抜き出します。根が絡まっている場合は、手でほぐしたり、ナイフで切り離したりします。
2.株を分ける
トケイソウの株を2~3個に分けます。分けるときは、茎や根が傷つかないように注意しましょう。分けた株はそれぞれ鉢植えまたは地植えにします。
3.水やりをする
株分けしたトケイソウに水やりをします。水やりは乾燥しない程度に行います。水やり過ぎると根腐れの原因になります。
4.回復させる
株分けしたトケイソウを日陰の場所に置いて回復させます。直射日光は避けましょう。気温は20~25℃程度が適しています。回復するまでに約2~3週間かかります。
トケイソウの種の取り方
トケイソウの種は、花が終わった後にできる果実から採取します。果実は緑色から黄色やオレンジ色に熟します。
熟した果実は割れやすいので、割れる前に収穫しましょう。収穫時期は品種によって異なりますが、一般的には夏から秋にかけてです。
トケイソウの種の採取方法は以下のとおりです。
1.果実を割る
熟した果実を手で割ります。果実の中には多数の種が入っています。種は黒くて光沢があり、粘液で覆われています。
2.種を取り出す
果実から種を取り出します。粘液が付いたままではカビや虫にやられやすいので、水洗いして粘液を落とします。
3.種を乾燥させる
水洗いした種をキッチンペーパーなどで水気を拭き取ります。その後、日陰で風通しの良い場所に広げて乾燥させます。乾燥には数日かかります。
4.種を保存する
乾燥した種を保存容器に入れます。保存容器は密閉できるものが適しています。保存容器にはラベルを貼って品種名や採取年月日などを記入しましょう。保存場所は冷暗所が適しています。
もしトケイソウが枯れたらチェックすべきポイント
トケイソウが枯れる原因としては、以下のようなものが挙げられます。
水やりの不適切
水やりは乾燥しない程度に行うことが大切です。水やり過ぎると根腐れを起こしたり、水やり不足だと葉がしおれたりします。特に夏は高温になるので、日中の水やりは避けて朝夕に行いましょう。
水やりは鉢土の表面が乾いたら行います。水やり量は季節や気温によって変えましょう。夏は多めに、冬は少なめにします。水やり時には鉢底から水が出るまで与えて、余分な水は捨てましょう。
肥料の不足や過剰
肥料は春から秋の成長期に適量を与えることが必要です。肥料不足だと生育が悪くなったり、花付きが悪くなったりします。肥料過剰だと根や茎に焼けを起こしたり、病害虫に弱くなったりします。
肥料は春から秋に月1回程度、緩効性化成肥料や有機質肥料を施します。液体肥料を使う場合は10日に1回程度、適度に希釈したものを与えます。真夏や真冬は肥料を控えましょう。
日当たりや温度の不適切
トケイソウは日当たりの良い場所を好みますが、直射日光は避けましょう。直射日光に当たると葉焼けを起こしたり、花色が褪せたりします。
また、気温は20~25℃程度が適しています。寒さに弱い種類は冬は室内に入れて管理しましょう。
トケイソウは日当たりの良い場所に置きますが、直射日光は避けて半日陰にします。気温は20~25℃程度が適しています。寒さに弱い種類は冬は室内に入れて管理しましょう。室内ではガラス越しの日光が当たる場所に置きます。
病気や害虫の被害
トケイソウはアブラムシやカイガラムシなどの害虫によってダメージを受けることがあります。害虫によって栄養分を奪われたり、病原菌を媒介されたりします。
また、立ち枯れ病という病気にも注意が必要です。立ち枯れ病は土壌中の菌に感染すると、茎や葉が黒く枯れてしまう病気です。
トケイソウは風通しの良い場所に置き、過湿や過乾燥を避けることが病気や害虫の予防になります。アブラムシやカイガラムシなどの害虫は、発見したら殺虫剤で駆除しましょう。立ち枯れ病にかかった植物は、他の植物に感染しないように早めに処分しましょう。
トケイソウと他の植物との違い
トケイソウと似ている植物として挙げられる他の植物との違いについてご紹介します。
- クレチマスとトケイソウの違い
- テッセンとトケイソウの違い
- パッションフルーツとトケイソウの違い
特に違いについて聞かれることの多い上位3つの測物との違いについてまとめます。
クレマチスとトケイソウの違い
クレマチスとトケイソウは、同じキンポウゲ目ですが、科や属は異なります。
クレマチスとトケイソウは、花の大きさや色、形などに違いがあります。クレマチスの花は4~8枚の花弁(正確には萼片)で構成されており、色や形は品種によってさまざまです。花弁の数は多くても12枚程度です。
クレマチスとトケイソウは、開花時期にも違いがあります。
クレマチスの開花時期は品種によって異なりますが、一般的には春から秋にかけてです。春咲き系、夏咲き系、秋咲き系に分類されます。
テッセンとトケイソウの違い
テッセンとトケイソウはどちらもキンポウゲ科のつる性の植物で、花の形や色が似ていますが少しことなります。
テッセンは、中国に自生している野草で、花弁は6枚で白や紫色が多く、雄しべが花弁化しています。花言葉は「甘い束縛」「縛り付ける」「高潔」などです。
パッションフルーツとトケイソウの違い
トケイソウとパッションフルーツは、同じトケイソウ科トケイソウ属の植物ですが、異なる品種です。
パッションフルーツは、トケイソウの中でもクダモノトケイソウという種類で、果実が食用になります。
トケイソウにも果実が付きますが、観賞用のものは可食部が少なく甘みがないことが多いです。
トケイソウの種類一覧
トケイソウの種類一覧を表で作ってみました。トケイソウは約500種ほどありますが、ここでは代表的なものを紹介します。
| 和名 |
学名 |
花色 |
耐寒性 |
備考 |
| トケイソウ |
Passiflora caerulea |
白~青紫 |
強い(-15℃) |
最も一般的な種類 |
| パッションフルーツ |
Passiflora edulis |
白~紫 |
弱い(5℃) |
食用の果実がなる |
| クダモノトケイソウ |
Passiflora quadrangularis |
赤~ピンク |
弱い(10℃) |
大きな果実がなる |
| オオミノトケイソウ |
Passiflora incarnata |
紫~ピンク |
強い(-10℃) |
薬用にもなる |
| ベニバナトケイソウ |
Passiflora coccinea |
赤~オレンジ |
弱い(5℃) |
鮮やかな花が咲く |
| キトリナ |
Passiflora citrina |
黄色 |
弱い(10℃) |
黄色い花が珍しい |
| バナナパッションフルーツ |
Passiflora mollissima |
桃色~白 |
弱い(5℃) |
バナナ型の果実がなる |
| レッドインカ |
Passiflora miniata var. miniata |
赤 |
弱い(5℃) |
花弁が多く重なる |