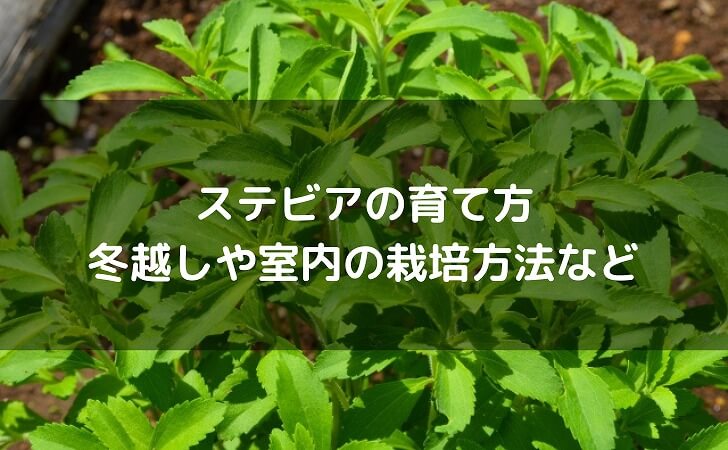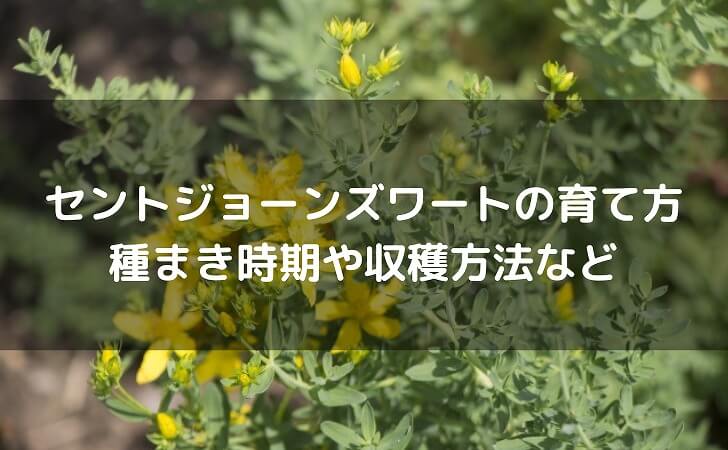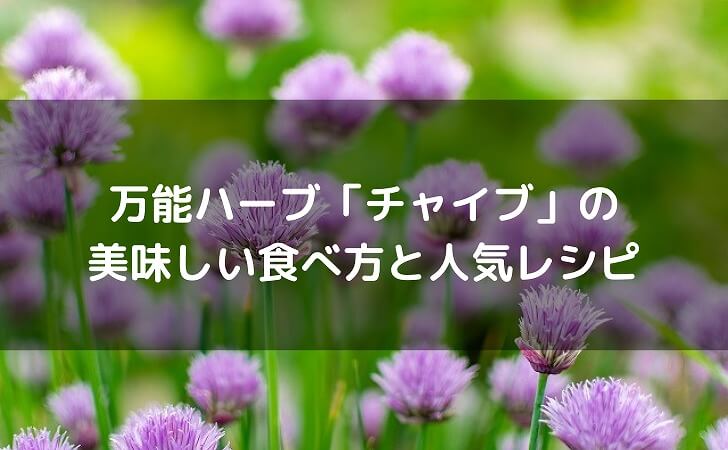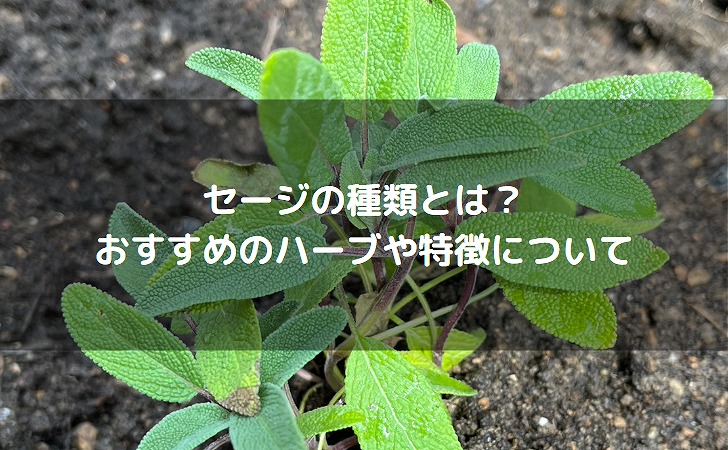ステビアは、南米原産のキク科の多年草で、葉に含まれる甘味成分が砂糖の約300倍という特徴を持つハーブです。
ステビアは熱帯から亜熱帯の原産であり寒さに弱く、日本では冬に霜に当たると枯れてしまうことからなかなか育てにくい植物だと感じている方も多いと思います。
しかし、適切な管理をすれば冬越しや室内での栽培も可能ですし、挿し木や株分けなどの方法で簡単に増やすこともできます。
この記事では、ステビアの育て方について、冬越し・室内の栽培方法を中心に、挿し木などによる増やし方などについてご紹介します。
ステビアの種まきと苗植え(地植え)の時期と方法
ステビアは、種まきや苗植えの時期によって生育や収穫量に影響が出るので注意が必要です。
ステビアの種まきは春まきと秋まきがあり、春まきは3月~4月頃、秋まきは9月~10月頃に行います。
種まき準備として、ステビアの種を水に浸して吸水させておきます。充分に水を吸った種を湿った土に蒔いて軽く覆い土をして完了です。ステビアの種の発芽に必要な温度は22℃前後と高いので発芽までは日当たりと温度管理に気をつけます。
(ただし、ステビアの種は発芽率が低い(諸説ありますが25%~50%くらい)ので、苗を購入するか親株から茎を挿し木して増やす方が簡単です。)
発芽したら混み合ったところを間引きながら、本葉が4枚くらい出た頃に一度小さな鉢に1本ずつ植え替えます。
苗植え(地植え)に関しては、春から夏(5月~6月)にかけて行います。
植え付ける場所は日当たりが良く風通しの良い場所を選びます。ステビアは日光を好むので、太陽光がよく当たるようにします。
ただし、30℃を超すと暑さで弱ることがあるので、真夏は直射日光を避けるか日陰に移動させます。鉢植えやプランターに植える場合は、草丈が大きくなるので大きめの容器を利用します。
用土は水はけの良い肥えた土が適しています。
苗を植え付ける際には、ステビアの根に付いている土はほぐさずにそのまま植え付けるようにすれば、根が傷むのを防ぐことができます。
ただし、育苗ポットから苗を取り出した際に、根がびっしり廻るようにして伸びて詰まってしまっているような苗ならば、根を軽く少しほぐしてから植え付けを行うようにした方がその後の生育には好ましいです。植え付け間隔は30~40cmくらい空けておくのが望ましいです。
なお、ステビアは種から育てると個体差が大きくなりがち(甘味の強い優秀な株もあれば逆に苦みがある株もできます。)なので、ステビアを増やす際には、甘味成分・ステビオサイドの含有量には品種差・個体差があることを考慮して、含有量の多い良質な個体を選んで挿し木で増やして栽培するようにすると良いでしょう。
ステビア栽培に適した土づくり
ステビアは適湿な土壌環境を好み乾燥がやや苦手ですが、過湿になると根が腐ってしまうことがあるため注意が必要です。
栽培に適した土を作るためには、以下のとおり赤玉土や腐葉土などを混ぜ込んで水はけの良い土を用意すると良いでしょう。
- 赤玉土(小粒か中粒)6:腐葉土4くらいの割合で混ぜる
- 20~30cmくらいよく攪拌しながら混ぜ込む
- 1週間程度土を落ち着かせる
なお、赤玉土は水分を保持しながらも余分な水分を排出する働きあるため水はけのよい土にでき、腐葉土は有機物や微生物を供給して土の肥沃さを高める働きがあります。
この2つを混ぜ合わせることで、ステビアが好む水はけが良く、栄養分が豊富な土が作れます。
ステビア栽培に適した環境(日当たり・水やり・肥料)
ステビアは日光を好むので、太陽光がよく当たる場所で栽培するようにします。
ただし、30℃を超すと暑さで弱ることがあるので真夏は直射日光を避けるか日陰に移動させましょう。
ステビアは適湿な土壌環境を好み乾燥がやや苦手ですが、過湿になると根が腐ってしまうことがあるため、水やりは土の表面が乾いた頃にたっぷりと水を与えます。
まだ乾かないうちに水やりすると土の中が過湿状態になり、根が腐って株がダメになることがあるので気をつけましょう。(冬は休眠しているので水やりの回数を少なくし、乾かし気味にします。)
ステビアは肥料を与えることで生育が促進されるので、肥料は植え付ける際に、予めゆっくりと効く粒状の肥料を土に混ぜ込んでおきます。
その後、春から秋の間は2~3ヶ月に1回程度、追加として油かすなどの固形肥料を少量与えるくらいで充分です。
また、風通しの良い場所に植えることで、湿気や病害虫の発生を防ぐことができますので、植え付けや鉢植えの置き場所を決める際には考慮しておきたいところです。
ステビアをプランターや鉢植えで育てる方法
ステビアはプランターや鉢植えでも十分に育てられます。
寒さに弱いので、初めから鉢植えで育てて冬には室内へ移動させて栽培する方が育てやすいと言えます。
適した土壌や環境、水やりや肥料は地植えの時と同じで問題ないので、上記の項を参考にして最適な環境で栽培してみてくださいね。
ただ。夏場の室内は特に高温になりやすいので日陰に移すなど気をつけたいところです。
ステビアの室内での育て方と水耕栽培のやり方
ステビアは日本では鹿児島以南でしか露地栽培できないほど寒さに弱いため、室内で鉢植えやプランターで育てられることが多いです。
室内の優しく日光の差し込む場所で育てると、葉がやわらかくて甘味の強いステビアに育つのが特徴です。
室内で鉢植えで育てる場合は地植えの時と同様の育て方で良いですが、夏の暑さには地植えの時以上に注意しましょう。
また、鉢植えやプランターでの栽培の他にも、水耕栽培も可能です。
水耕栽培で種から育てる場合は、湿らせたスポンジに種まきして発芽を待ちますが、前述したとおりステビアの種の発芽率は低いので少し多めに種まきをしておいた方が無難です。
水耕栽培のやりかたは以下のとおりです。
ステビアの水耕栽培のやり方
- 水耕栽培キット、ネットポット、水耕栽培液、発泡スチロールを用意する
- ネットポットにステビアの苗を植え、根が水に浸かるように調整する
- 発泡スチロールにネットポットの穴を開けて、水耕栽培液を入れた容器にセットする
- 水耕栽培液の水位とpHを定期的にチェックして、必要に応じて補充や調整を行う
- ステビアの葉が十分に成長したら収穫する
水は2日〜3日に1回は交換し、新しい水で育てて株を清潔に保つのがポイントです。
水耕栽培の詳しいやり方はこちらのページにまとめました。
[surfing_other_article id=”345″]ステビアの収穫時期
ステビアの収穫時期は、草丈が20cm以上に伸びてくる7月〜11月に行います。
ステビアは生育旺盛で株がよく茂るので、生育期は随時葉を収穫して利用できます。
甘味成分のステビオサイドが一年のうちで一番高くなるのは花が終わったあと(10月下旬から11月の上旬)なので、保存目的の場合はこの時期に収穫すると良いです。
収穫は株元から刈り取って束にし、風通しの良い日陰でよく乾燥させた後保存しましょう。
ステビアの冬越しの方法
ステビアは寒さに弱いですが霜や寒風に当てなければ0℃くらいまでは耐えられ、多年草でもあり宿根草でもあるので、冬に枯れても根は残り春に新芽が出てきます。
地植えのまま冬越しをする場合は、霜や凍結の心配がある場合ではマルチング(株元をワラや落葉堆肥、ピートモスなどで覆う)などの防寒対策が欠かせません。
日本では鹿児島以南でしか露地栽培できないと言われているので、多くの場合は室内で冬越しすることになると思いますが、室内においてはエアコンの風に長く当てると葉が乾燥して枯れ込んでしまう点には注意が必要です。
なお、ステビアは冬に休眠期に入るので水や肥料を少なめに施しましょう。
前述したとおり、無事に冬越しできていれば春になると新芽が出てくるので、その時期に剪定や植え替えを行います。
ステビアの摘芯・剪定・切り戻しのやり方
ステビアは、適切な剪定・摘芯・切り戻しを行えば、枝数や葉の量を増やし収穫量をアップさせることができます。
ステビアは、春に新芽が出てくると急速に成長しますが、この時期に茎の先端の芽を摘むことを摘芯といいます。摘芯をすることで、茎のワキから新しい芽が伸びてきて枝分かれし、株がふさふさと茂ってくれます。摘芯は株全体が均等になるように行うのがコツです。
ステビアは、夏から秋にかけて白い小さな花を咲かせますが、この花は葉の収穫には不要なものであり、むしろ栄養を奪って葉の成長を阻害します。
そのため、花芽が出たら茎ごと切り落とす必要がありますが、この作業を剪定といいます。剪定をすることで、株に余分なエネルギーを消費させずに葉の成長を促進します。
剪定は株元から風通しが良くなるように行いましょう。
ステビアは、冬に休眠期に入ります。この時期に株元から刈り取って乾燥させることを切り戻しといいます。切り戻しをすることで、株を冬越ししやすくし、翌年も元気に芽吹くことができます。切り戻した茎や葉は乾燥させて保存しておきましょう。
ステビアは摘芯・剪定・切り戻しによって樹形や収穫量を調整できるハーブです。摘芯・剪定・切り戻しの方法を覚えて、甘味成分が豊富なステビアをぜひ楽しんでみてくださいね。
ステビアの挿し木・水挿しでの増やし方
ステビアは種まきでも増やせますが、発芽率が低いだけでなく個体差が大きい(甘さもバラつきがある)ため、挿し木や水挿しで増やす方が一般的です。
初夏(6月頃)に挿し木をすると発根率が比較的高いので、この時期に行うのが良いでしょう。
種から増やすと品質に違いが出やすいですが、新芽を利用して挿し木をすることで同じ品質のステビアを増やすことができます。
ステビアの挿し木での増やし方は以下のとおりです。
- 生き生きとした充実している部分の茎を選ぶ
- わき芽の上を1cmほど残して切る
- 下葉を落として節の下は2cmほど切る
- 水に1時間程度挿して、吸水させる
- 湿らせたさし床に穴を開け、垂直に挿す
3週間くらいするとわき芽が伸びてきているのが確認出来たら、発根したことがわかります。
根を傷つけないように株を掘り上げて、鉢上げを行います。
なお。水挿しで増やす場合は、以下のとおり発根させるようにしましょう。
- 上記の挿し木の手順1~3を行う
- 切った茎を一輪挿しやコップなどに水を入れて挿す
- 日当たりと風通しの良い場所に置く
- 水を数日おきに取り替えます
- 約2週間ほどで発根するので根の先を確認する
発根しているのが確認出来たら鉢上げを行います。
挿し木も水挿しも難易度が高くないので、適切な増やし方を行えば一株から何株も増やすことができます。
寄せ植えでステビアと相性の良いハーブ
砂糖の200~300倍の甘味を持つ天然の甘味料として使えるステビアは、寄せ植えにしてキッチン周りに置いておくと、摘みたてで最も美味しい状態で楽しむことができます。
そんなステビアとの寄せ植えに相性の良いハーブは、以下のようなものがあります。
| 相性の良いハーブ | 補足 |
| ミント | ステビアとミントを一緒に植えると、爽やかな香りと甘みが楽しめます。ミントはステビアと同じく日当たりを好みますが、水やりは少なめで大丈夫です。ミントはステビアよりも草丈が低いので、寄せ植えでは前方に配置すると良いでしょう。 |
| ローズマリー | ステビアとローズマリーを一緒に植えると、芳醇な香りと甘みが楽しめます。ローズマリーはステビアと同じく日当たりを好みますが、乾燥に強いので水やりは控えめで大丈夫です。ローズマリーはステビアよりも草丈が高いので、寄せ植えでは後方に配置すると良いでしょう。 |
| ハニーステビア | ステビアとハニーステビアを一緒に植えると、軽やかな甘味と花のような香りが楽しめます。ハニーステビアはステビアの仲間で、同じような育て方ができます。ハニーステビアはステビアよりも小ぶりなので、寄せ植えでは中央に配置すると良いでしょう。 |
以上のように、ステビアと相性の良いハーブは、香りや甘みを引き出すものや、育て方や草丈が合うものがおすすめです。
ステビア栽培(農法)について
ステビア栽培とは、キク科植物のステビアの抽出物を農作物に与えることで、土壌の改良や作物の品質向上を図る農法です。(ステビア農法とも呼ばれます)
ステビアにはダイオキシンやニコチンなどの有害物質を分解する作用や、微生物の活性化、病原菌の抑制などの効果があります。ステビア栽培では、ステビアの品種や栽培方法、抽出方法などによって、農作物の甘味や生育、日持ちなどに違いが出ることが報告されています。
ステビア栽培は、環境と健康に配慮した農業として注目されています
中でも、いちご(やよいひめなど)・トマト・みかん・メロンなどの生産にステビア栽培が用いられているのが有名です。
ステビアの育て方に関するQ&A
ステビアの育て方に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。
- ステビアの栽培は危険なの?
- ステビアの花は食べられる?
- ステビアが枯れる原因は?
- かかりやすい病害虫と対策は?
上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。
ステビアの栽培は危険なの?
海外では一部の国で禁止されたり、安全性に疑問が持たれたりすることもあったことから、ステビアの栽培は危険なのか気になる人は多いでしょう。
栽培自体に危険性は全くありませんが、ステビアを栽培して利用することによる危険性を危惧している声については、結論から言うと注意点を守る上では大きな危険性はありません。
まず前提として、ステビアは日本では1971年に商品化されて以来、食品添加物として認められています。その上で注意点としてはステビアの摂取量が挙げられます。
ステビアに含まれる甘味成分のステビオシドやレバウディオサイドによって性ホルモンが減少した事例がありますが、海外でステビアを摂取した子供の「テストテロン」という男性ホルモンが減少したという報告に基づいているものです。
また、ステビアは体内に蓄積しやすい性質を持つため、長期間摂り続けると何らかの症状が出るのではないかと懸念されています。
そのため、ステビアを摂取する際には、適量を守ることが大切です。日本ではステビア抽出物の1日摂取許容量(ADI)は4mg/kgと定められていますが、これは体重50kgの人なら200mgまでということです。
以上のことから、ステビアは性ホルモンや血糖値に影響を与える可能性があるため、妊娠中や授乳中の女性や、糖尿病や高血圧などの持病がある人は避けた方が良いでしょう。
ステビアの花は食べられる?
ステビアはキク科の植物で、葉に含まれる甘味成分が注目されているハーブですが、ステビアの花は食べられるのでしょうか?
結論から言うと、ステビアの花は食べられます。
ステビアの花は白い小さな花が集まった穂状の花序で、9月から11月にかけて咲きます。ステビアの花にも甘味成分が含まれており、葉よりもさらに甘い味がします。そのため、食べるときは少量で十分です。
ステビアの花は、そのまま生で食べたり、サラダやデザートにトッピングしたりすることができます。また、ドライフラワーにしてハーブティーに入れたり、シロップやジャムに煮詰めたりすることもできます。ステビアの花は、色も香りも控えめなので、他の食材やハーブと組み合わせやすい特徴があります。
また、ステビアの花は抗酸化作用や抗菌作用などの効果もあることから、美肌効果や免疫力アップといった健康や美容にうれしい効果も期待できます
その一方で、ステビアの花を食べるときも前述したとおり、ステビアの摂取量には注意して楽しむようにしましょう。
ステビアが枯れる原因は?
ステビアを育てていると枯れてしまうことがありますが、その原因は何でしょうか?
ステビアが枯れる原因として考えられるのは、以下のようなものです。
| 枯れる原因 | 補足 |
| 水やりの不足 | ステビアは乾燥に弱いので、水やりを怠ると葉がしおれて枯れてしまいます。 |
| 水やりの過剰 | 水やりが多すぎると根腐れや病気の原因になります。水やりをしすぎると、葉が黄色くなって枯れてしまいます。 |
| 寒さ | ステビアは耐寒性がないので冬場は霜や雪から守ってください。寒さに当たると葉が茶色くなって枯れてしまいます。 |
| 病害虫 | ステビアはアブラムシやハダニなどの害虫にやられやすいので、定期的に葉をチェックして害虫が見つかったら自然農薬などで駆除してください。害虫に食べられると葉が穴だらけになって枯れてしまいます。 |
以上のように、ステビアが枯れる原因は様々ですが、基本的な管理をしっかり行えば防ぐことができます。
かかりやすい病害虫と対策は?
ステビアを育てていると病気や害虫にやられることがありますが、その原因と対策は何でしょうか?
ステビアがかかりやすい病気としては、根腐れや灰色カビ病などがあります。根腐れは水やりの過剰や排水の悪さが原因で、根が腐って枯れてしまいます。
灰色カビ病は湿度の高さや通気の悪さが原因で、茎や葉に灰色のカビが発生して枯れてしまいます。
これらの病気の対策としては、水やりは適度に行い、土が乾いたら水やりをするようにします。また、鉢底に穴を開けて水はけを良くし、風通しの良い場所に置きます。
ステビアがかかりやすい害虫としては、アブラムシやハダニなどがあります。
アブラムシは茎や葉の裏側に集まって吸汁し、葉がしおれたり穴だらけになったりします。
ハダニは乾燥した環境で発生しやすく、葉の表面に白い斑点を作ったり、細い糸を張ったりします。これらの害虫の対策としては、定期的に葉をチェックして、害虫が見つかったら自然農薬などで駆除するほか、葉水を与えて湿度を保ちます。
以上のように、ステビアがかかりやすい病害虫と対策は様々ですが、基本的な管理をしっかり行えば防ぐことができます。
ステビアは自宅で収穫して甘味料として使える便利なハーブです。病気や害虫に負けないように丁寧に育ててください。
まとめ:ステビアの育て方について
ステビアは甘味料として人気のあるハーブですが、寒さに弱いために日本では冬に霜に当たると枯れてしまいます。
冬越しする場合は、鉢植えにして室内や温室に移動させるか、マルチング(株元をワラや落葉堆肥、ピートモスなどで覆う)などの防寒対策が欠かせません。(暖かい地方に限り地植えで冬越し可能)
この冬越しさえできれば、ステビア采配はそれほど難しいことはなく、ステビアの好む環境を整えれば地植えでも室内でも問題なく栽培できるはずです。
また、ステビアは挿し木や水挿しなどの方法で簡単に増やすことができますが、ベストのタイミングの夏から秋にかけて挿し木などで増やしてみても良いでしょう。ステビアを上手に育てて、自家製の甘味料を楽しむのも良いですね。