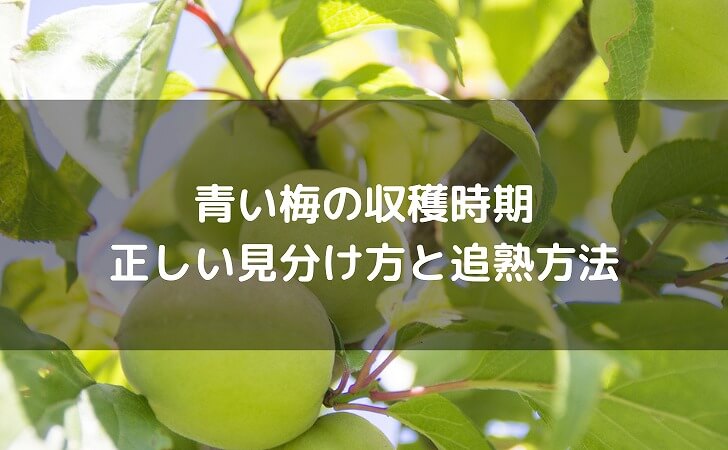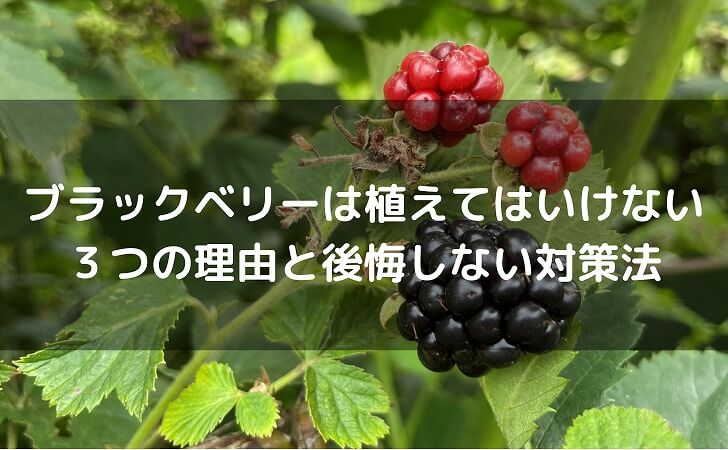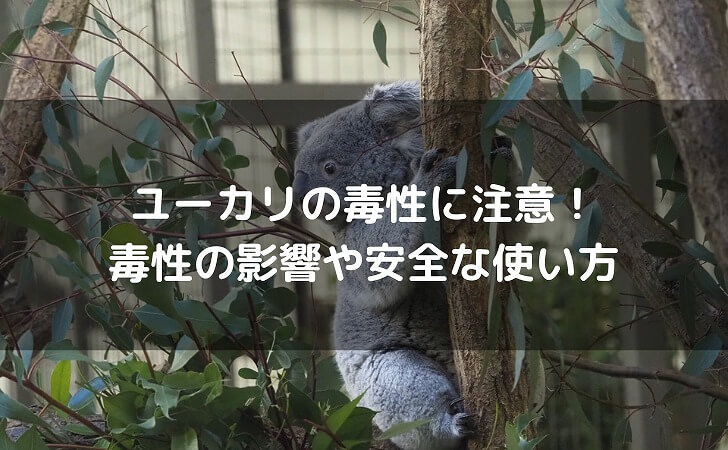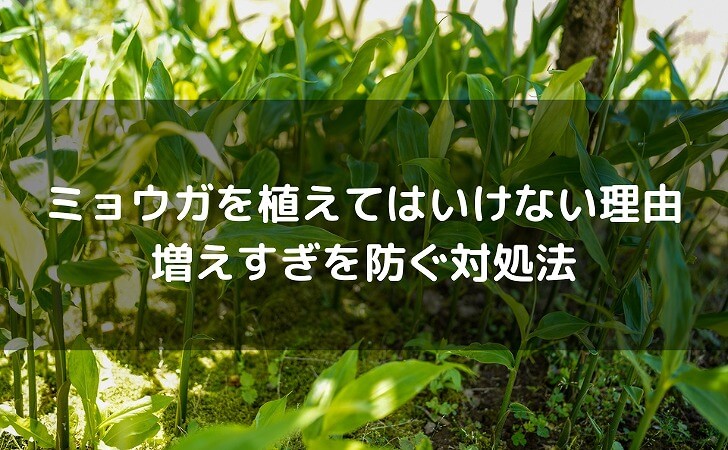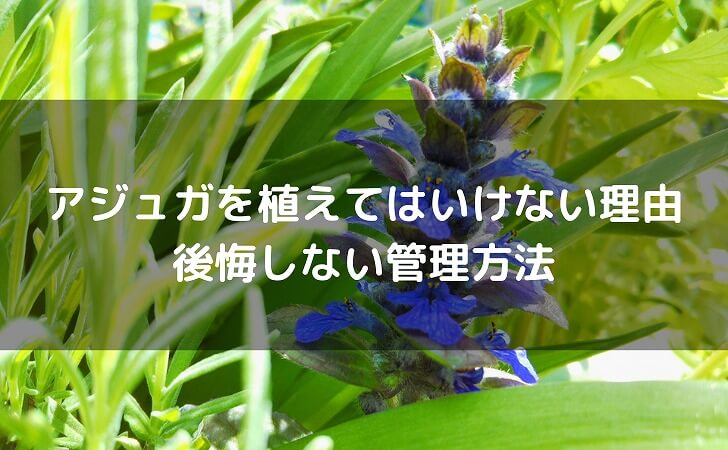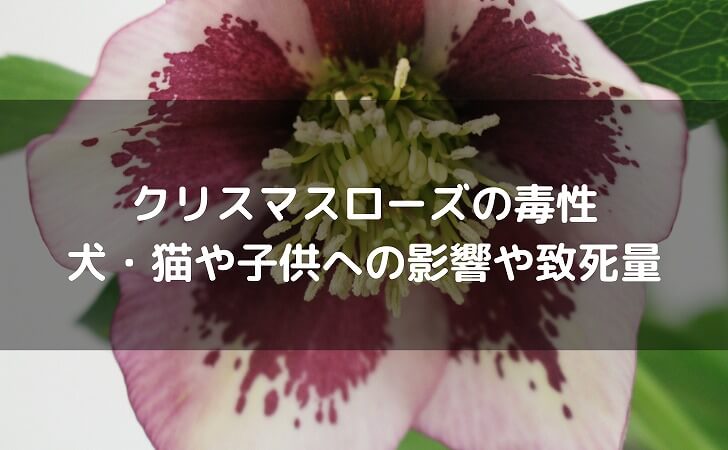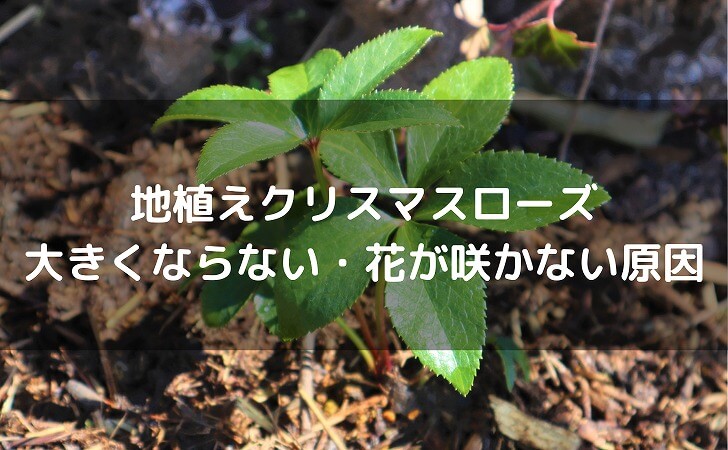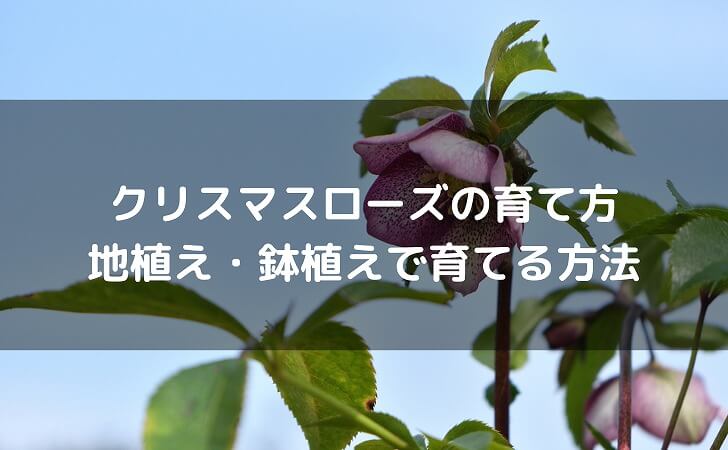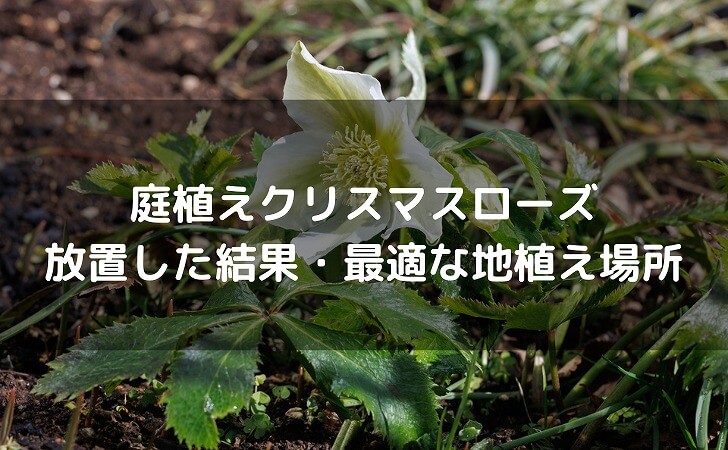梅の木に実がなると嬉しくなって収穫したくなりますが、まだ青い梅の段階では収穫は早過ぎます。
梅酒や梅ジャム、梅干しなどの加工用として収穫する場合であれば問題ありませんが、そのまま食べる場合は、梅が熟するのを待つ必要があります。
この記事では、梅の収穫時期の見分け方や追熟方法のほか、青梅に含まれる毒性についてもご紹介しています。
梅の収穫時期の基本
梅の収穫時期は地域や品種によって異なりますが、一般的には6月から7月にかけてが最適です。
梅の実が十分に成熟し、色づき始めたら収穫のサインです。完熟した梅は自然と落下することもあるため、地面に敷いたシートで受け止めると良いでしょう。
収穫した梅は、梅酒や梅干し、ジャムなどの様々な加工用に用いられるため、用途によって適切な収穫時期は異なります。
収穫が早過ぎる梅の特徴と画像

収穫が早過ぎる梅は、その成熟度によっていくつかの特徴があります。
まず、色が十分に変わっていないことが挙げられます。早摘みの梅は、通常の紫や黄色ではなく、青みがかった色をしています。この段階の梅は果肉が硬く酸味が強いため、食べるときの味わいが劣ることがあります。
さらに、早摘みの梅は保存性が低く、すぐに傷んでしまうことも特徴です。これらの梅は、梅酒や梅干しにする際にも、風味が十分に出ないことがあるため、注意が必要です。
梅の収穫時期の見分け方

梅の収穫時期の見分け方としては、次の3つが判断材料となります。
- 色
- 硬さ
- 香り
成熟した梅は、表面が滑らかで光沢があり色も鮮やかな紫や黄色に変わります。
また、梅の実を軽く押してみて少し柔らかくなっているかどうかを確認します。硬すぎる場合は未熟で、柔らかすぎると過熟の可能性があります。
梅の香りも重要な指標で、甘酸っぱい香りが強くなると収穫のタイミングです。
青い梅の毒性について
未熟な青い梅にはアミグダリンが多く含まれているため、生での摂取は避けるべきです。
このアミグダリンは、体内でシアン化物に変わる可能性があり、毒性があるとされています。
梅を加工する際には、十分な熟成を待つかアミグダリンを分解するために塩漬けや熱処理を行うことが重要です。
なお、青梅の毒性については農林水産省のページでも情報提供されているので、参考にしてみてくださいね。
ここでは、青梅の追熟期間や毒性の変化、致死量についてお伝えしていきます。
青梅は何日で食べられるようになるのか
青梅を食べられる状態にするには追熟が必要ですが、通常だと収穫後の梅は室温で約1週間から2週間で追熟され、食べ頃になります。
追熟を促進するためには、梅を新聞紙に包み、リンゴやバナナなどのエチレンガスを放出する果物と一緒に置く方法があります。
このプロセスにより、梅は自然に柔らかくなり、甘酸っぱい風味が増します。
ただし、追熟中は梅の状態を定期的にチェックし、カビや腐敗がないかを確認することが大切です。
青梅の毒はどうなるのか
青梅に含まれるアミグダリン自体は毒性を持つ成分ですが、梅を適切に処理することで安全に摂取できるようになります。
例えば、梅干しを作る際には塩漬けという過程があり、この塩分がアミグダリンを無毒化する役割を果たします。
また、梅酒を作る場合であれば、アルコールがアミグダリンを分解し毒性を減らす効果があります。
当然ながら、追熟させるだけでもアミグダリンは減少していくので、安心して食べられるようになります。
青い梅の致死量
アミグダリンには毒性がありますが、致死量に達するには通常の食事では非現実的な量を摂取する必要がある程度の毒性しかありません。
例えば、成人であれば数キログラムの青梅を一度に摂取することになります。
ただ、致死量に至らないだけで健康に影響を及ぼす可能性はあるため、青梅を食べる際には適切な加工方法を通じてアミグダリンを減らすことが推奨されます。
収穫が早過ぎた梅の追熟方法

収穫が早過ぎた梅の追熟方法には、自然な熟成を促進するいくつかの手法があります。
まず、梅を室温で保管し、通気性の良い場所に置くことで、ゆっくりと熟成させます。また、梅を新聞紙や紙袋に包んで、他の果物、特にリンゴやバナナと一緒に置くと、これらの果物が放出するエチレンガスが梅の熟成を促進します。
ただし、追熟させる際には、梅が傷まないよう定期的にチェックし、カビや腐敗の兆候がないか確認することが重要です。
梅の実がなる季節と旬の時期
梅の実がなる季節は、主に春から初夏にかけてです。日本では、梅の花が咲くのは2月から4月にかけてで、これが梅の実が成熟する前兆となります。
梅の実は、花が散った後の5月から6月にかけて徐々に大きくなり、旬を迎えます。
旬の梅は、果肉が柔らかくジューシーで、甘酸っぱい風味が特徴です。この時期に収穫される梅は、新鮮なまま食べるのはもちろん、梅酒や梅干し、ジャムなどの加工食品にも最適です。
梅がスーパーで売られている時期
梅がスーパーで売られている時期は、主に梅の収穫時期に合わせており、日本で新鮮な梅が市場に出回るのは5月下旬から7月にかけての時期が一般的です。
この時期は梅の実が最も豊富で、様々な品種が店頭に並ぶので、この時期に梅酒や梅干しの材料として、または生食用として梅を購入するのが良いでしょう。
まとめ:梅の収穫時期と青い梅の毒性や追熟方法
梅の収穫時期は、地域や梅の活用方法によって適切な時期が異なるものの、一般的には6月から7月にかけてが適期です。
熟す前の青梅には毒性が含まれるので生食は避けた方が良いですが、追熟や加工の過程で毒性が弱まってきます。
青梅の追熟は、風通しの良いところへ置いておけばできますが、梅を新聞紙に包んでリンゴやバナナなどのエチレンガスを放出する果物と一緒に置くと促進されます。
とても魅力的なハーブである梅を活用する際の参考にしてみてくださいね。