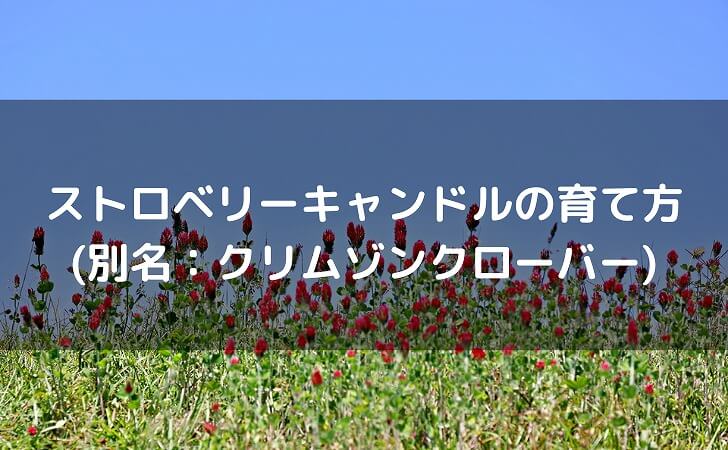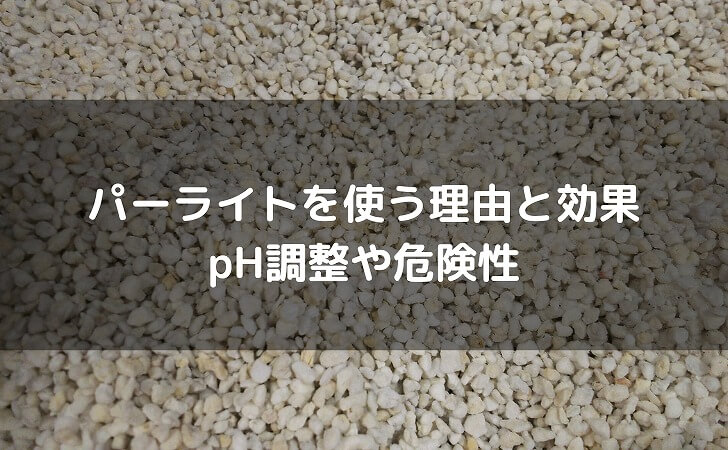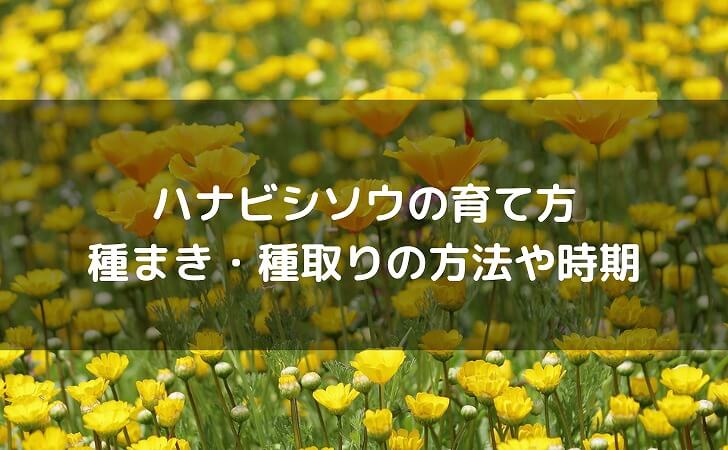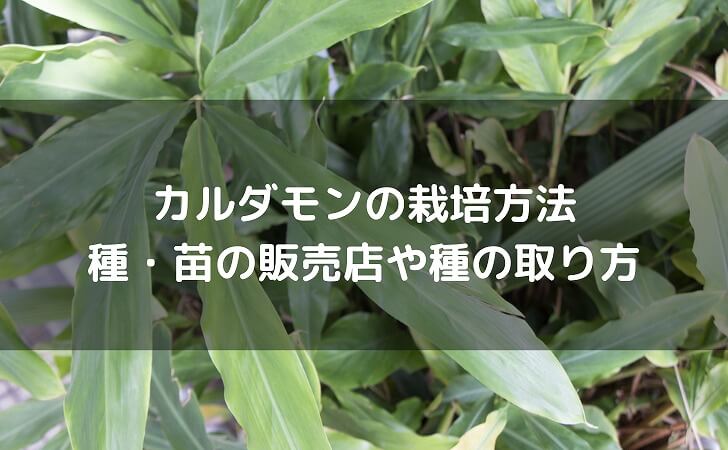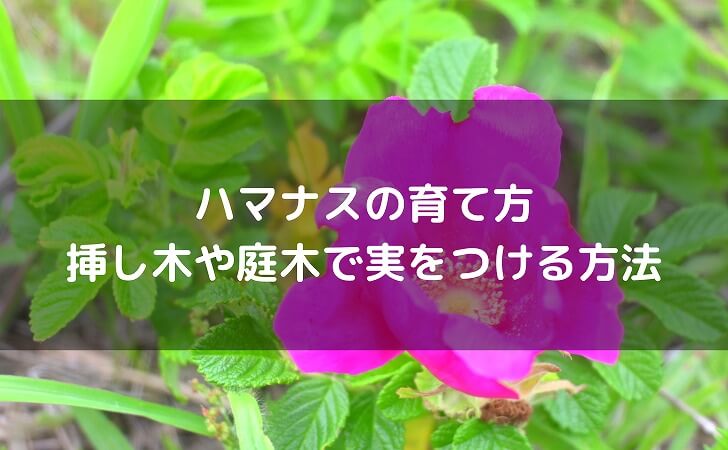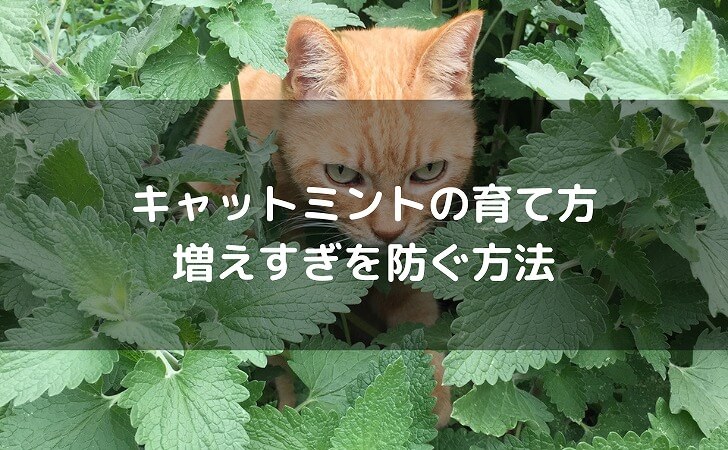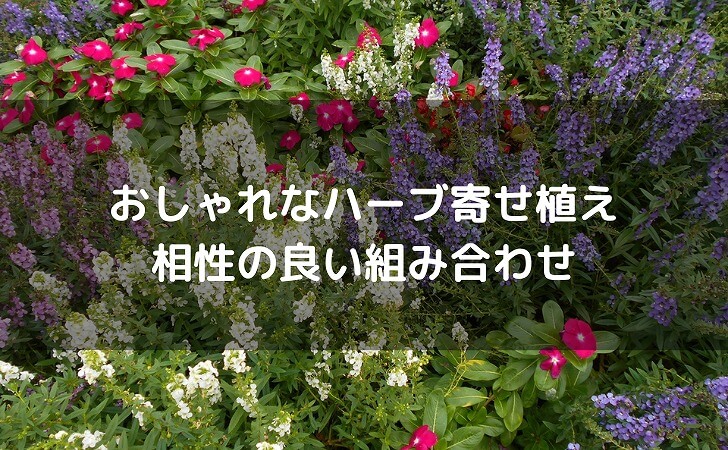春になると、いちごのような赤い花を咲かせるストロベリーキャンドルが目を引きます。この花はクローバーの仲間で、別名クリムゾンクローバーとも呼ばれます。
一見難しそうに見えますが、実は育て方はとても簡単で、種まきから開花まで初心者でも失敗しにくい草花です。
ストロベリーキャンドルは、耐寒性が強くて暑さに弱いという特徴があるため、日本では一年草として扱われています。しかし、夏越しできれば、翌年も同じ場所で花を咲かせることができます。また、こぼれ種でも増やすことも可能です。
この記事では、ストロベリーキャンドルの育て方について、種まきの時期や方法、日常の管理や剪定のコツなどをお伝えします。
ストロベリーキャンドルの種まき時期と方法
ストロベリーキャンドルの発芽温度は20℃~25℃で、種まき時期は地域によって異なります。
一般的な地域では、夏の暑さが落ち着いた9月~10月頃に種まきをします。この場合、次の春に開花させることができます。北海道などの寒冷地では、夏の暑さの影響を受けにくいため、8~9月頃に種まきをします。この場合、次の春~初夏が開花時期です。
ストロベリーキャンドルの種まき方法は、以下のとおりです。
- 育苗箱やポリポットに水はけの良い用土を入れる。
- 用土を湿らせる。
- 種をバラバラにまいてから約2mm程度覆土する。
- 種と用土が密着するように指で軽く押さえる。
- 霧吹きで水やりをする。
約3~5日で発芽するので、発芽したら日当たりの良い場所に移します。双葉が開いたら、株と株の間を約20cm~30cm開けて植え付けます。
ストロベリーキャンドルは直播きが適している
ストロベリーキャンドルは直播きが適していると言われていますが、その理由は以下のとおりです。
- 根が弱く移植に弱い
- 寒さに強く発芽しやすい
- 種子散布で自然に増える
少しだけ補足を以下に記します。
1.根が弱く移植に弱い
ストロベリーキャンドルは根が細くて弱く、移植すると根が傷ついてしまうことがあります。そのため、移植の必要がない直播きの方が根付きやすくなります。
2.寒さに強く発芽しやすい
ストロベリーキャンドルは寒さに強く、冬の間に種をまいておくと春に発芽します。寒さに当たることで花芽形成も促されます。そのため、秋から冬にかけて直播きするのがおすすめです。
3.種子散布で自然に増える
ストロベリーキャンドルは開花後に種子を散布します。その種子が自然に地面に落ちて発芽することで、翌年も同じ場所で咲かせることができます。そのため、直播きすることで自然な感じで増やすことができます。
ストロベリーキャンドルの発芽日数と間引きの方法
ストロベリーキャンドルの発芽日数は、約3~5日です。種まきから発芽までの間は、用土が乾燥しないように霧吹きで水やりをしましょう。
また、ビニールなどをかぶせて湿気を保つと発芽率が高まります。発芽したら覆いを外して日当たりの良い場所に移します。
ストロベリーキャンドルの間引きの方法は以下のとおりです。
| 時期 | 双葉が開いたら間引きをして、本葉4~5枚程度になった頃も間引きをします。 |
| 方法 | 勢いのある株を残し、成長の遅い株や密集した株を抜きます。根が傷つきやすいため株の根元の土を少しほぐすと根が切れにくくなります。 |
| 間隔 | 株と株の間は約20cm~30cm開けます。(鉢植えなら1鉢1株にします) |
ストロベリーキャンドル栽培に適した環境(用土づくり・水やりと肥料の与え方)
ストロベリーキャンドルは、根粒菌という微生物が窒素を合成できるため、肥料があまり必要ない丈夫な植物です。
日当たりと風通しの良い場所で育てることで特に問題なく育てられますが、基本的な環境づくりについてご紹介します。
【用土づくり】
水はけの良い用土を使用します。鉢植えの場合は市販の草花用培養土を使います。赤玉土(小粒)6:腐葉土:3パーライト:1の配合で混ぜると良いでしょう。
【水やり】
苗のうちや植え付け直後は土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをします。一度根づくとある程度の乾燥にも耐えるので乾かし気味に管理します。鉢植えの場合は鉢皿に溜まった水はこまめに捨てましょう。
【肥料】
マメ科の植物は根粒菌が窒素を合成できるため肥料はあまり要らないです。下葉が黄色く変色した場合は薄い液肥を与えましょう。肥料を与えすぎるとアブラムシが発生する可能性があります。
ストロベリーキャンドルの地植えの時期と方法
ストロベリーキャンドルは、暑さに弱く、気温が高いと上手に育たなかったり枯れてしまったりします。
そのため、9月や10月になり暑さがやわらいできたら早めに種まきや植え付けを行い、7月や8月の暑さが厳しくなる前には開花が終わるように育てるのがポイントです。
地植えにする場合は、横に広がる性質があるため広いスペースを確保してから植え付けましょう。 鉢植えやプランターに植える場合は、15cm〜20cmほど株間をあけると良いでしょう。
ストロベリーキャンドルは、日当たりと風通しのよい場所で育てましょう。 多湿が苦手なため、ジメジメとした環境では上手に育ちません
ストロベリーキャンドルを鉢植え・プランターで育てる方法
ストロベリーキャンドルは、地植えだけでなく鉢植えやプランターで育てることができます。
鉢植えやプランターで育てる場合は、以下の点に注意しましょう。
| 用土 | 水はけの良い用土を使用します。市販の草花用培養土や赤玉土(小粒)と腐葉土とパーライトの配合土などがおすすめです |
| 水やり | 土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと水やりをします。ただし、蒸れに弱いので水の与えすぎは避けます。花・葉・茎に水が直接かからないように注意しましょう。また、鉢皿に溜まった水はこまめに捨てるようにします。 |
| 肥料 | 根粒菌が窒素を合成できるため、基本的に肥料は必要ありません。下葉が黄色く変色した場合は薄い液肥を与えましょう。 |
| 置き場所 | 日当たりと風通しの良い場所で育てましょう。日光が当たらない環境では花付きが悪くなります。 |
ストロベリーキャンドルの植え替え時期と方法
ストロベリーキャンドルは、日本では一年草の扱いなので植え替えは必要ありません。種まきや苗の植え付けをした後は、そのまま育てて開花させます。ただし、鉢植えやプランターで育てる場合は、鉢やプランターの大きさに合わせて適宜植え替えを行います。
ただ、ストロベリーキャンドルはマメ科の植物なので、移植を嫌う性質があります。そのため、定植後に根付いてから植え替えを行うと繊細な根が傷ついて花が咲かなくなってしまうことがあります。
もし植え替えをする場合は、種まきや苗の植え付け直後か開花後に行いましょう。根が鉢やプランターに張り付いていないうちか、花が終わってからが最適です。
鉢やプランターは、株よりも一回り大きいものを選びます。根詰まりを防ぐためにも余裕を持たせましょう。
ストロベリーキャンドルの花が咲く時期と香り・花言葉
ストロベリーキャンドルの花が咲く時期は春で、4月~6月にかけて赤い花を咲かせます。花茎をまっすぐに伸ばし、その先に赤色の花模様がキャンドルの炎のような形をした赤色の花を咲かせます。
クローバーの仲間ですが、シロツメクサやクローバーのような甘い香りはしません。そのため、香りを楽しみたい方には向きませんが、切り花や寄せ植えとしても色合いを楽しむことができます。
ストロベリーキャンドルには、下に挙げる5つの花言葉があります。いずれの花言葉もストロベリーキャンドルの特徴的な花姿からイメージされたものになっています。
| 胸に火を灯す | ストロベリーキャンドルは、紅色の花模様がまるでキャンドルの炎のような形をしたハーブです。そのため炎をイメージした「胸に火を灯す」という花言葉がつけられました。とても素敵な花言葉ですね。 |
| 煌めく愛 | 「煌(きら)めく愛」もまた、ストロベリーキャンドルの炎のような花姿と花色から生み出されたもの。ストロベリーキャンドルの花がいくつも咲きながら風にゆれる様子は、愛を奏でる恋人たちのようです。とても情熱的で印象深い花言葉です。 |
| 素朴な愛らしさ | ストロベリーキャンドルは、園芸品種の豪華なお花というよりは、むしろ雑草に近い素朴な植物。そんなストロベリーキャンドルの草姿を如実にあらわしているのが「素朴な愛らしさ」という花言葉でしょう。 |
| 魅惑 | ストロベリーキャンドルは、赤色の花色が鮮やかで目を引く植物です。そのため、「魅惑」という花言葉もあります。赤色は情熱や欲望を象徴する色でもありますから、魅惑的な雰囲気を感じさせるかもしれません。 |
| 美しい心 | ストロベリーキャンドルは、肥料があまり必要ない丈夫な植物です。そのため、「美しい心」という花言葉もあります。美しい心とは、素直で清らかで優しい心のことです。ストロベリーキャンドルは、そんな心を持つ人に贈りたいお花です。 |
ストロベリーキャンドルを剪定・切り戻しする方法と目的・時期
切り戻しの時期は、花が終わってから夏にかけてです。花が終わる時期は、品種や栽培環境によって異なりますが、一般的には5月~6月頃に行います。
切り戻しの目的は、花が終わった後に枯れた茎や葉を取り除き、株の見栄えを良くすることと、翌年の開花を促すことです。
- 枯れた花穂や茎を株元から切り取る。
- 残った葉や茎を半分くらいに切り戻す。
最後に、切り口に傷がつかないように注意しながら、水やりや肥料を適度に与えます。水やりは土が乾いたら行い、肥料は液肥や遅効性の肥料を少量与えましょう。
ストロベリーキャンドル栽培で気をつけたい病害虫
本来であればストロベリーキャンドルは多年草ですが、日本では夏に枯れる一年草として扱われています。そのため、病害虫に強く、特に気をつける必要はありません。
しかし、完全に病害虫にかからないというわけではありません。以下に、ストロベリーキャンドルにつきやすい病害虫とその対策を紹介します。
| アブラムシ | アブラムシは、葉や茎の先端に集まり、吸汁して植物の生育を阻害します。また、ウイルス病の媒介者となることもあります。アブラムシが発生したら、早めに殺虫剤を散布しましょう。 |
| カタツムリ・ナメクジ | カタツムリやナメクジは、葉や茎を食害して穴をあけたり切断したりします。特に雨上がりや湿気の高い時期に注意が必要です。カタツムリやナメクジが発生したら、早朝や夕方に駆除しましょう。また、ナメナイトやネキリベイトなどの餌型殺虫剤を散布すると効果的です。 |
| 立枯病 | 立枯病は、土壌中の菌が根から侵入して植物全体を枯らす病気です。特に高温多湿の時期に発生しやすく、一度発生すると治すことが難しいです。立枯病が発生したら、感染した植物は早めに処分しましょう。また、予防のために株間を広くとったり、水やりを控えめにしたりしましょう。殺菌剤は、カリグリーンやベニカマイルドスプレーなどがおすすめです。 |
ストロベリーキャンドルの夏越しの注意点
ストロベリーキャンドルは本来は多年草ですが、暑さに弱いため日本では夏に枯れる一年草として扱われています。
そのため、夏越しをする際には特別な注意が必要です。
以下に、ストロベリーキャンドルの夏越しの注意点とその対策をご紹介します。
暑さに弱い理由
ストロベリーキャンドルは、暑さに弱いのが最大の特徴です。高温多湿の環境に長くさらされると、葉が黄色くなったり、茎が倒れたりして枯れてしまいます。
暑さに弱い理由は、根粒菌という窒素を合成する菌が高温に耐えられないためです。
夏越しの対策
暑さに弱いストロベリーキャンドルを夏越しするには、以下の対策が有効です。
- 日陰や涼しい場所に移動する
- 風通しをよくする
- 水やりを控えめにする
- 殺菌剤や殺虫剤を散布する
次に、もう少し詳しくお伝えしていきます。
1.日陰や涼しい場所に移動する
ストロベリーキャンドルは、日当たりと風通しの良い場所を好みますが、夏の直射日光は避ける必要があります。直射日光が当たると、葉や茎が焼けて枯れてしまうことがあります。そのため、午前中だけ日光が当たる半日陰や涼しい場所に移動しましょう。
また、室内で育てる場合は、エアコンや扇風機で温度を下げると良いでしょう。
2.風通しをよくする
ストロベリーキャンドルは、湿気にも弱いです。湿気が高いと、病気や害虫の発生や増殖につながります。特に立枯病やアブラムシなどに注意が必要です。そのため、風通しをよくすることで、湿気を減らしましょう。
また、株間を広くとったり、葉や茎を切り詰めたりして、空気の流れを良くすることも効果的です。
3.水やりを控えめにする
ストロベリーキャンドルは乾燥にも強いので、水やりは土の表面が乾いたら行う程度で十分です。水やりを多くすると、根腐れや病気の原因になります。特に夏場は水分の蒸発が早いため、水やりの回数や量を減らすことで、土の温度を下げることができます。
4.殺菌剤や殺虫剤を散布する
ストロベリーキャンドルは病害虫に強い植物ですが、夏場は病害虫の発生や増殖が活発になります。特に立枯病やアブラムシなどに注意が必要です。
そのため、予防のために殺菌剤や殺虫剤を散布することがおすすめです。殺菌剤は、カリグリーンやベニカマイルドスプレーなどが効果的です。殺虫剤は、ベニカXスプレーやパイベニカVスプレーなどがおすすめです。
ストロベリーキャンドルの耐寒性と冬越しの方法
夏越しの項で記載したとおり、本来は多年草でありながらも日本の夏では枯れてしまうことが多いストロベリーキャンドルですが、耐寒性は高く-2℃まで耐えることができます。
ストロベリーキャンドルの花が咲くためにはある程度の寒さが必要なので、外の気温が-2℃以下でなければ冬でも外で育てると良いですが、下回る場合は屋内で冬越資する必要があります。
こうした特徴を踏まえて、ストロベリーキャンドルを冬越しのポイントを3つお伝えしていきます。
- 霜よけをする
- 室内に移動する
- 土を乾燥させない
それぞれの項目の詳細について個々にお伝えしていきます。
1.霜よけをする
ストロベリーキャンドルは、霜に弱いです。霜が降りると、葉や茎が傷んだり、枯れたりしてしまいます。そのため、霜が降りる可能性がある場合は、霜よけをしましょう。
霜よけには、ビニールや不織布などの軽い素材を使います。重い素材を使うと、植物に負担がかかります。霜よけは夕方から朝方まで行い、日中は外して風通しを良くします。
2.室内に移動する
ストロベリーキャンドルは、室内でも育てることができます。室内に移動する場合は、日当たりの良い場所に置きましょう。窓際やベランダなどがおすすめです。
室内では暖房器具や乾燥機などで空気が乾燥することがあります。その場合は、加湿器や水を入れた皿などで湿度を保ちます。
3.土を乾燥させない
ストロベリーキャンドルは、乾燥にも強いです。しかし、冬場は土が凍結したり乾燥したりすることがあり、それにより根が傷んだり枯れたりすることがあります。
そのため、土の表面が乾いたら水やりをしますが、水やりは控えめに行い、水分過多にならないように注意します。
以上が、ストロベリーキャンドルの耐寒性と冬越しの方法です。基本的に丈夫な植物なので、適切な管理を心がければ問題なく育てることができます。赤い花を長く楽しみましょう。
ストロベリーキャンドル栽培で気をつけたい病害虫
ストロベリーキャンドルは耐寒性が高く、肥料もあまり必要ない丈夫な植物ですが、病害虫には注意が必要です。
以下に、ストロベリーキャンドル栽培で気をつけたい病害虫とその対策は次のとおりです。
| 病害虫 | 症状と対策 |
| アブラムシ | 茎や葉に吸汁する害虫で、植物の生育が阻害されたり、ウイルス病の媒介者になったりします。水やりや剪定でアブラムシを洗い流すか殺虫剤を散布して対処します。 |
| カタツムリ・ナメクジ | 葉や茎を食害する害虫で、植物の葉が穴だらけになったり茎が切断されたりします。水やりを控えめにして土を乾燥させることで予防します。駆除はビールや酢などを入れた罠を設置したり殺虫剤や駆除剤を散布します。 |
| うどんこ病 | 葉に白い粉状の菌糸が生える病気で、植物の光合成能力が低下したり葉が枯れたりします。うどんこ病は高温多湿な環境で発生しやすく、風雨で感染が広がるので、日当たりと風通しの良い場所に植えることや殺菌剤を散布して対処します。 |
ストロベリーキャンドルの増やし方
ストロベリーキャンドルの増やし方としては、種まきしか方法はありません。
ハーブで多くみられる増やし方として、挿し木・挿し芽・株分けなどがありますが、いずれもストロベリーキャンドルには適しません。
ただ、種は簡単に採取可能なので、上手に育てて種を採取して種まきをすることで、どんどん増やすことが可能です。
次は、ストロベリーキャンドルの種取の方法をお伝えしていきます。
ストロベリーキャンドルの種取りの方法
ストロベリーキャンドルの種取りに適した時期は、6月~7月です。花が終わったら摘み取らずにそのままにしておくと、下から黒ずんできます。その時点で乾燥させると、きれいな赤い色の種が採れます。
種取りの方法は以下のとおりです。
- 花穂が黒ずんできたら花穂の下の方から切り取る。
- カットした花穂を風通しの良い場所で乾燥させる。
- 乾燥した花穂を手でこすって種を取り出す。
- 種は紙袋に入れて種まきの時期まで冷暗所にて保管する。
乾燥させる際は、束ねて吊るすか、新聞紙などで包んで平らに置く方法があります。乾燥させる時間は、気温や湿度によって異なりますが、約1週間から2週間程度で良いでしょう。
種は小さくて赤い色をしています。保管する際は、湿気や虫害に注意してください。
ストロベリーキャンドルの育て方に関するQ&A
ここでは、ストロベリーキャンドルの育て方に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。
- ストロベリーキャンドルは多年草ですか?
- ストロベリーキャンドルは緑肥に使える?
- ストロベリーキャンドルは外来種?
- ストロベリーキャンドルは北海道でも育つ?
- 白い花を咲かせるストロベリーキャンドルの品種は?
- ストロベリーキャンドルの苗はどこで買える?
上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。
ストロベリーキャンドルは多年草ですか?
ストロベリーキャンドルは、原産地では多年草として生育しますが日本では夏の暑さに弱く、一年草として扱われることが多いです。
多年草として毎年楽しむためにも、夏越しに気を付けて育ててみても良いかもしれませんね。
ストロベリーキャンドルは緑肥に使える?
ストロベリーキャンドルは、緑肥植物としても優れています。緑肥植物とは、枯れた花や枝葉を処分せずにそのまま寝かせておいて、次に同じ場所で栽培する作物の肥料として混ぜ込める植物のことです 。
マメ科の植物は根粒菌の働きで窒素を合成できるため、次の作物に必要な窒素分を供給して土壌改良にも役立つほか、病害虫の発生を抑制する働きもあります。
ストロベリーキャンドルは外来種?
ストロベリーキャンドルはヨーロッパから西アジアにかけて分布している植物で、明治時代に牧草として日本に移入された外来種です。
しかし、野生化することはほとんどなく自然環境に影響を与えることもありません。そのため、環境省の侵略的外来種リストには含まれていません。
ストロベリーキャンドルは北海道でも育つ?
ストロベリーキャンドルは、北海道などの寒い地域でも育てることが可能です。
北海道では夏の暑さの影響を受けにくいため、夏(8~9月頃)に種まきをしましょう。次の春~初夏が開花時期です。
育て方次第では夏越しも可能なので、多年草として育てることもできるでしょう。
白い花を咲かせるストロベリーキャンドルの品種は?
ストロベリーキャンドルの花色は赤が主流ですが、白い花を咲かせる品種もあります。
切り花では「クリスタルキャンドル」や「ストロベリーキャンドル(白)」という名前で流通しています。種や苗は赤花がほとんどですが、稀に白花も見つけることができます。白い花は赤い花よりも優しい印象を与えます。
白い花を咲かせるストロベリーキャンドルの品種は、赤い花と同じように育てることができます。
ストロベリーキャンドルの苗はどこで買える?
ストロベリーキャンドルの苗は、園芸店やネットショップで購入することができます。
ホームセンターでは私がこれまで探してきた範囲では販売されているのを確認したことがありませんが、店舗や地域によっては販売されているところもあるかもしれません。
楽天などのネットショップやメルカリで「ストロベローキャンドル 苗」などと検索して販売状況を確認できますが、実際に届く苗を確認することは困難なので注意が必要です。
ホームセンターやメルカリでのハーブの苗の販売についてはこちらのページにまとめているので、参照してみてください。
[surfing_other_article id=”1081″]まとめ:ストロベリーキャンドルの育て方のポイント
ストロベリーキャンドルは、春に赤い花を咲かせるクローバーの仲間です。育て方は簡単で、種まきから開花まで初心者でも上手に育てられます。種まきは地域によって夏か秋に行い、日当たりと風通しの良い場所に植えます。水やりは土が乾いたら行い、肥料は控えめにします。剪定は花後に行って種を採取するか、こぼれ種で増やすことができます。
ストロベリーキャンドルは暑さに弱いため、夏越しは難しいですが、可能ならば涼しい場所に移動させたり、水やりを増やしたりしてみましょう。また、マメ科の植物なので緑肥植物としても利用できます。枯れた後は土に混ぜ込んで次の作物の肥料にすることができます。
ストロベリーキャンドルは、春の庭やベランダを華やかにするだけでなく、切り花やドライフラワーとしても楽しめる植物です。ぜひ一度育ててみてください。