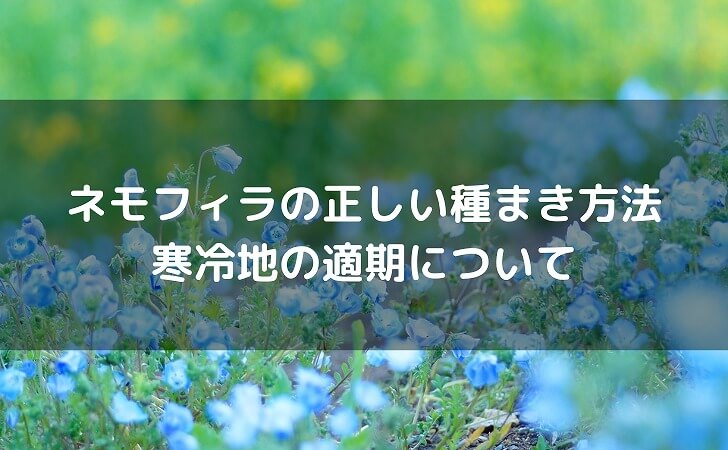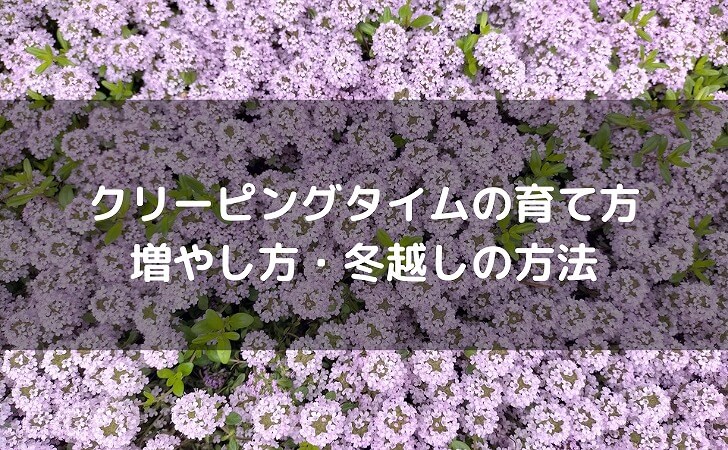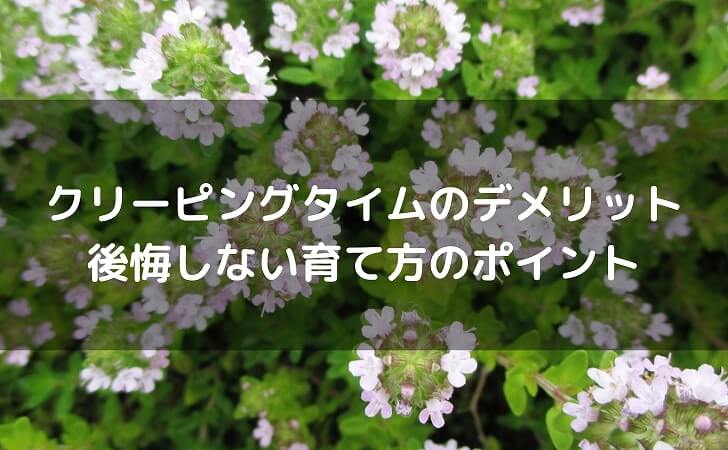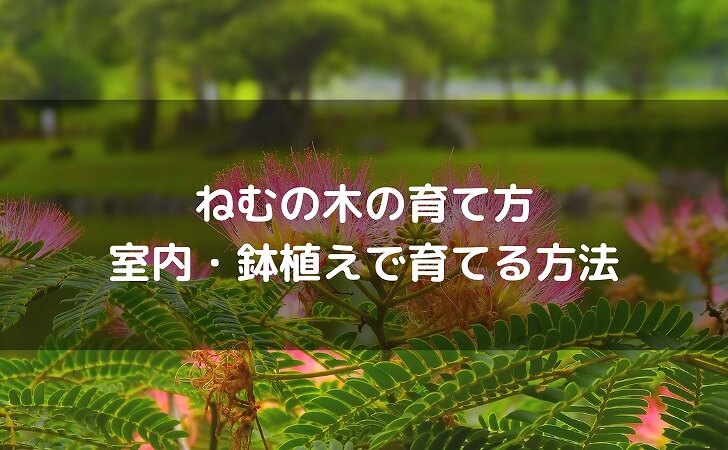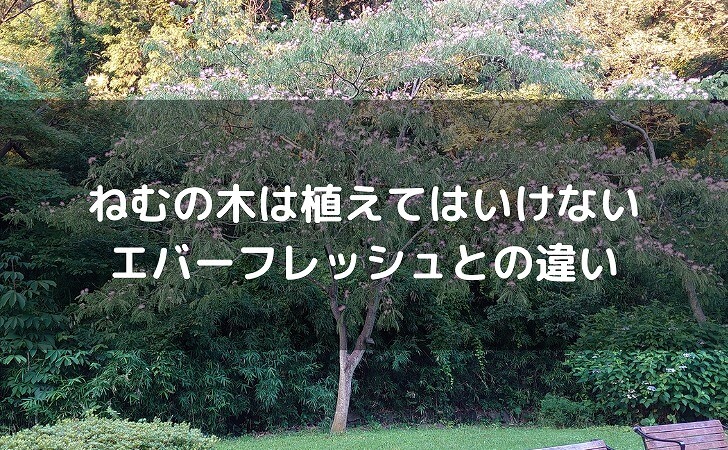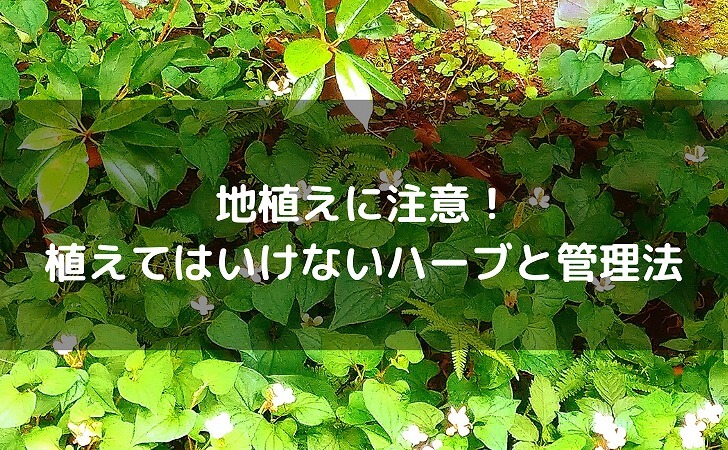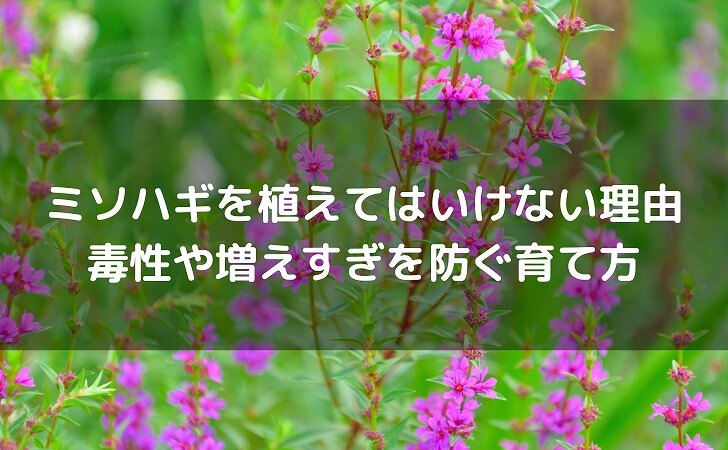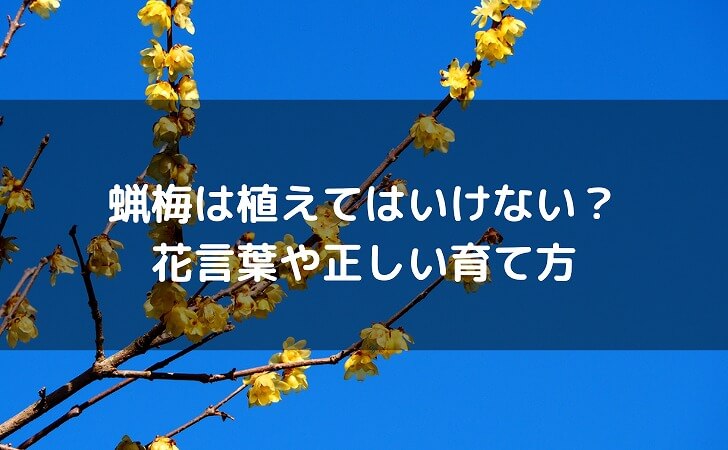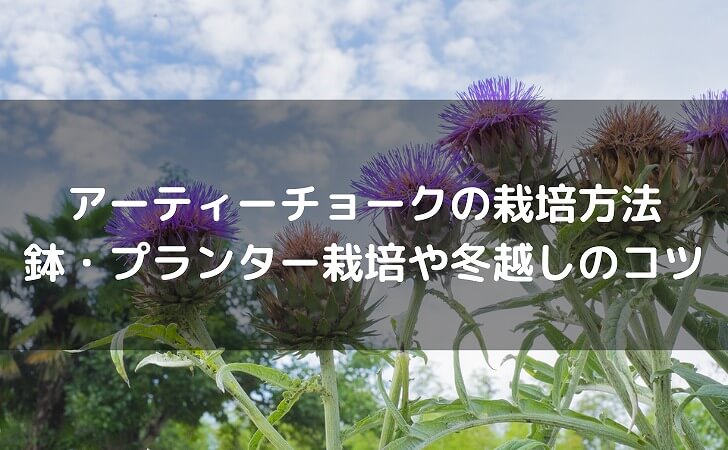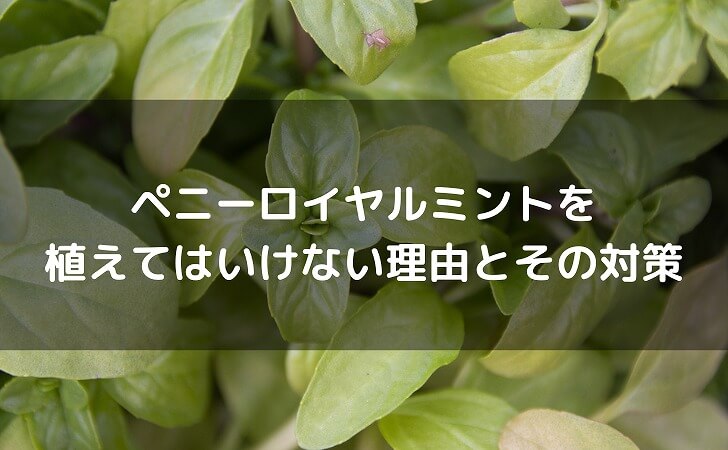冬の寒さに負けない美しい花を咲かせる蝋梅(ロウバイ)。その香りと色は、日本のお正月に欠かせない植物です。
しかし、蝋梅には毒性があったり花が咲かない時期が長いことから「蝋梅は庭に植えてはいけない」と言われることがあります。また、花言葉は怖いと言われることもあります。
こうしたことから蝋梅を植えてみたいという方でも心配になってしまうかもしれませんが、それほど大きなデメリットもないので安心して育ててみて欲しいと思います。
この記事ではそんな蝋梅の育て方や考えられるデメリットとその対策、鉢植えでの育て方についても紹介します。
リンク
蝋梅は庭に植えてはいけない3つの理由

蝋梅を庭に植えてはいけないと言われる理由は、主に以下の3つが挙げられます。
- 毒があるため
- 花を咲させづらいため
- 鳥害にあう可能性があるため
それぞれの理由と対策についてもう少し詳しくお伝えしていきます。
毒があるため
蝋梅の実には強い毒性があります。
アルカロイドの一種カリカンチンが含まれており、誤って食べたり触れたりすると中枢神経系に影響を与えて、強直性痙攣や呼吸促迫などの中毒症状を起こす可能性があります。
庭に植える場合は小さな子供やペットが誤って口に入れることの無いように注意が必要です。
花を咲かせづらいため
蝋梅は、種から育てると5年以上、苗木からでも開花までに数年は必要な植物なので、花を鑑賞することが主な目的で植える場合は、長い間待つ必要があります。
また、剪定の時期や方法を間違えると花芽がつかなくなったり、花が咲かなくなったりする可能性もあるので注意が必要です。
鳥害にあう可能性があるため
蝋梅は特にヒヨドリが蝋梅の花や蕾を好んでつついて、せっかく花を咲かせたのに食べられてしまう可能性があります。
また、好んで鳥が集まると糞や鳴き声が周囲の迷惑になることがあるので、蝋梅を植える場合は場所にも気を付けておきたいところです。
蝋梅を植える際に気を付けるべきこと
蝋梅を庭に植えてはいけないと言われる理由はありますが、植える際に気を付けることで、必ずしも蝋梅を諦める必要はありません。
蝋梅を植える際に気を付けるべきポイントをまとめます。
- 子どもやペットが実を食べないようにする
- 正しい時期と方法で剪定を行う
- 鳥害対策を行う
それぞれの方法について補足をしていきます。
子どもやペットが実を食べないようにする
子どもや犬猫などのペットが誤って蝋梅の実を食べないようにする必要があります。
物理的に囲いをするなどするのが有効です。
正しい時期と方法で剪定を行う
初めてだと難しく感じますが、正しい方法を知ることで適切な剪定を行うことができます。
蝋梅の時期と剪定方法については剪定の項をご参照ください。
鳥害対策を行う
蝋梅の鳥害対策としては、以下のような方法が考えられます。
- 防鳥網を張る
- 鳥の置物や風鈴を置く
- 別の場所に鳥の好きな餌を置く
ただし、鳥害対策にはメリットとデメリットがあるので、環境や好みに合わせて適切な方法を選んでみてください。
蝋梅を育てるのに適した環境

蝋梅は半日陰でも育てられますが、日当たりが良いほうが花付きが良くなります。また、冬に開花するため、寒風の当たらない場所を選ぶと良いでしょう。
蝋梅は移植を嫌う植物なので植える場所を選ぶ際は慎重に選ぶようにしたいところです。
蝋梅に適した用土づくりや水・肥料の与え方については次のとおりです。
用土づくり
蝋梅はそれほど土質は選ばない植物ですが、水はけの良い土が好ましいです。
市販の培養土が適していますが、自分で作る場合は赤玉土と腐葉土を7:3で配合すると適した土を作ることができます。
大きく育つため鉢植えには適さない植物ではありますが、鉢植えで育てる場合は小粒の赤玉土8:腐葉土2程度で混ぜた土で育てると良いでしょう。
[surfing_other_article id=”1598″]
水やりと肥料の与え方
基本的には地植えの場合は自然の降雨による水だけで良いですが、雨が降らない日が続くなどして表面の土が乾いたら、たっぷり水を与えます。乾燥しすぎると花付きが悪くなるので注意してください。
肥料は、冬の12月頃に寒肥として緩効性化成肥料を置き肥し、成長期の4~5月にも同様に与えると良いでしょう。
[surfing_other_article id=”1458″]
蝋梅の種まき時期と方法
蝋梅の種まきの時期は、実が熟した9~10月頃が適しています。この時期に種をまくと、冬に休眠して春に芽が出るようになります。
なお、種まきの方法は以下のとおりです。
- 実を収穫し、種子を取り出す
- 種子をひと晩水に浸ける
- ポットに3粒ずつ蒔く
- 土を3~4cmかける
- 温室で育てる
- 芽が出るまで水を切らさないようにする
一晩水に浸けた種は、水に沈んだ種だけを使うと良いです。(水に浮いた種は発芽率が低いので予め除外しておくようにします)
なお、蝋梅は種まきで比較的簡単に増やせるので、初心者の方でも安心して取り組める植物の一つです。
[surfing_other_article id=”1783″]
蝋梅を鉢植えで育てる方法
大きく育つ蝋梅は基本的には地植えが適しており、鉢植えでも育てることができますが、花付きが悪くなる可能性があります。
鉢植えで育てる場合は、以下の点に注意してください。
- 鉢は大きめのものを選ぶ
- 用土は水はけの良い培養土を使う
- 水やりは表面の土が乾いたら行う
- 肥料は冬と春に緩効性化成肥料を与える
- 植え替えは落葉期に行う
植え替えを嫌うので、できるだけ植え替えをしなくても良い鉢のサイズで育て始めるようにするのがコツです。
鉢植えでは花が咲かないのか
蝋梅を鉢植えで育てている場合、花が咲かないことがありますが、その原因として考えられるのは、以下のようなものが挙げられます。
- 鉢が小さすぎる
- 水やりが不足している
- 肥料が不足している
- 日当たりが悪い
- 剪定が不適切である
これらの問題を解決することで、蝋梅を鉢植えで育てたとしても花が咲く可能性が高まります。
蝋梅の植え替え時期
先ほども触れましたが、蝋梅は植え替えを嫌うので極力植え替えの必要がないようにしたいところですが、植え替えが必要になった場合は落葉期の11~12月、2~3月に行うようにします。
この時期に根鉢を崩さないように注意しながら、大きめの鉢に移します。用土は水はけの良い培養土を使うと良いでしょう。
蝋梅の花が咲く時期と香り
蝋梅の花が咲く時期は、12月~2月です。この時期に淡い黄色や白色の花を枝先に咲かせます。
花には甘い香りがあり、スパイスやハチミツ、バニラなどに似た香りだと言われています
蝋梅の花が咲くまで何年かかるのか
蝋梅の花が咲くまでの年数は、種から育てる場合と苗木から育てる場合で異なります。一般的には、以下のようになります。
種から育てる場合
開花までに5年以上かかります。育つ環境によっては10年以上かかることもあります。
苗木から育てる場合
開花までに数年かかります。購入した苗木の成長具合にもよりますが、花が咲かない時でも4年くらいは様子を見る必要があります。
蝋梅は冬に美しい花を咲かせる貴重な植物ですが、花を咲かせるには根気が必要です。
蝋梅の花を楽しみたい場合は、苗木を購入するか、接ぎ木や挿し木で増やすと早く花が咲くようになります
蝋梅に似た花には何があるか
蝋梅に似た花には、以下のようなものがあります。
これらの花は、蝋梅と同じく冬から春にかけて咲く黄色い花で、香りが良いという共通点があります。
しかし、形や大きさ、科や属などは異なるため、見間違うほどの見た目の類似点はありません。
なお、ミモザも時に「植えてはいけない」と言われることがあります。ミモザを庭に植えることのデメリットについてはこちらのページにまとめています。
[surfing_other_article id=”2302″]
ハマナスの育て方についてはこちらのページをご参照ください。
[surfing_other_article id=”1355″]
蝋梅の花言葉は怖いと言われる理由
蝋梅の花言葉は「ゆかしさ」「慈しみ」「先導」「先見」です。
これらの花言葉は、蝋梅が冬の寒さに耐えて早春に咲くことから、先駆者や先見者としての資質を表しています。
また、蝋梅の香りは心を和ませる効果があるとされており、ゆかしさや慈しみを感じさせるとも言われています。
しかし、蝋梅の花言葉には怖い説もあります。それは、「死」「死別」「死後の世界」です。
この花言葉は、蝋梅が冬枯れした木に咲くことから、死や別れを連想させるというものです。また、蝋梅の香りは霊界と繋がるという伝承があるため、死後の世界を示唆するとも言われています。
蝋梅の誕生花について
蝋梅の誕生花は1月8日です。この日は「成人の日」や「若者の日」と呼ばれることもあります。
この日に生まれた人は、蝋梅の花言葉と同じく、先見性やリーダーシップを持ち、周囲に優しく接することができる人だと言われています。
蝋梅を剪定する方法と目的・時期
蝋梅を剪定する目的は、以下のようなものがあります。
- 木の形を整える
- 花付きを良くする
- 病害虫の予防
- 風通しを良くする
蝋梅を剪定する方法は、以下の通りです。
- 花が終わった3~4月に行う
- 枯れ枝や病気の枝を切り落とす
- 花芽がついていない枝や花芽が少ない枝を切り落とす
- 重なっている枝や内側に向かっている枝を切り落とす
- 長く伸びた枝は適度に切り戻す
大きくなりすぎた蝋梅の剪定動画
大きくなりすぎた蝋梅の剪定方法が学べる動画としては、みどりと共に サントーシャじゅんさんの動画「【ロウバイの剪定】来年の花芽を養い、暴れた枝を整理する手入れ」がとても参考になります。
動画の概要を記載しておきます。
まず、根元から出ている「ひこばえ」と呼ばれる若い芽を2~3本残して切り落とします。ひこばえは栄養を奪ってしまうので、必要以上に残さないようにしましょう。
次に、樹形を乱している枝や、花芽のつかない枝を切ります。特に、幹や太い枝から上に向かって真っすぐ伸びた「徒長枝」と呼ばれる枝は、花芽がつきにくいので、つけ根から20cmほど残して短く切り詰めます。
さらに、一度花が咲いた枝や、枯れた枝や古い枝も切ります。ロウバイはその年に伸びた枝に花芽をつけるので、前年に咲いた枝には花芽はつきません。枯れた枝や古い枝は病気の原因になることもあるので、間引いておきます。
最後に、枝が密集している場所や、高さが気になる場所を間引いて、日当たりや風通しをよくします。ロウバイは日当たりが良いほうが花付きが良くなります。樹高は2~3mくらいに収まるように、できるだけコンパクトに仕立てましょう。
以上が、大きくなりすぎた蝋梅の剪定方法です。
剪定に必要な道具は、剪定ばさみと軍手、脚立を揃えて剪定してみてくださいね。
なお、専門の方に剪定を依頼する場合は、1本からでも剪定してくれるこちらの店舗が便利です。
>>いますぐ剪定の見積をとってみる

蝋梅の夏越しの注意点
蝋梅は夏にも水やりや肥料、病害虫対策が必要です。夏越しの注意点は以下のようになります。
- 水やりは土が乾いたら行う
- 肥料は与えない
- 病害虫に注意する
- 日陰に移動する
夏は蝋梅の休眠期で、花芽が形成されます。水やりは土が乾いたら行いますが、過湿にならないように注意してください。肥料は与えないでください。
病害虫には、アブラムシやカイガラムシ、ハダニなどが発生する可能性があるので、発見したら水洗いや殺虫剤で対処してください。
日陰に移動することで、直射日光や高温を避けることができます。
蝋梅の耐寒性と冬越しの方法
蝋梅は耐寒性が高く、-15℃まで耐えることができます。しかし、花芽や新芽は霜に弱く、凍害を受けることがあります。冬越しの方法は以下のとおりです。
霜よけをすることで、花芽や新芽を保護することができます。霜よけには、ビニールや不織布などを使います。
水やりを控えることで、根腐れや氷結を防ぐことができます。風通しを良くすることで、湿気やカビを防ぐことができます。
蝋梅を挿し木で増やす方法
蝋梅は挿し木でも増やすことができます。挿し木の時期は、6~7月頃です。
挿し木の方法は以下のとおりです。
- 新芽が伸びた枝から10~15cmの長さに切り取る
- 下の葉を取り除き、上の葉は半分に切る
- 切り口に発根促進剤を塗る
- ポットに水はけの良い用土を入れる
- 挿し木をポットに挿す
- ビニール袋などで覆う。
- 挿し木が根付くまで水切れしないようにする
以上の方法で蝋梅を挿し木によって増やすことができます。
挿し木のやり方の詳細はこちらのページをご参照ください。
[surfing_other_article id=”1593″]
蝋梅の育て方に関するQ&A
ここでは、蝋梅の育て方に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。
- 蝋梅の寿命はどれくらい?
- 蝋梅は風水的には良い?悪い?
- 蝋梅の実は方がいいって本当?
上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。
蝋梅の寿命はどれくらい?
蝋梅の木は他の樹木と同様に何百年と生き続けますが、鉢植えで育てる場合は寿命が短い傾向にあります。
また、剪定した場合に多いですが、花が咲かなかったりするなどで寿命を疑うこともありますが、正しい方法で育てている場合ではそれほど早く寿命が訪れることはありません。
蝋梅は風水的には良い?悪い?
蝋梅は風水的には良いと言われています。蝋梅は、お正月頃に咲く縁起のよい花として、中国では「瑞祥植物」や「雪中の四花」に数えられています。
その香りの高さと黄色い色は、全体運や金運を引き寄せるとされています。
庭に植えるなら、西の方角が吉とされています。盆栽や切り枝を使うなら、金運のコーナーに当たる、お部屋を入って左手奥に置くと効果的です。
蝋梅の実は取った方がいいって本当?
蝋梅の実は取った方がいいというのは本当です。蝋梅の実には毒があるので、食べたり誤って摂取したりしないように注意が必要です。
また、実を長く付けると樹の体力を奪ってしまうので、早めに取る方が樹の好影響を及ぼします。
まとめ:蝋梅は庭に植えてはいけない理由と適切な育て方
蝋梅は庭に植えてはいけないと言われる理由には、毒性や開花の難しさなどがあります。
しかし、これらの問題は食べたりしなければ影響がないものや、剪定や鳥害対策をすれば解決できるため、絶対に植えてはいけないと言うほどのデメリットとはなりえません。
むしろメリットも多く、冬に美しい花が咲き香りも良いので、庭木として魅力的な植物でもあります。
鉢植えでの育て方も紹介しましたが、大きく育つので、庭植えに向いています。蝋梅の花を咲かせるには根気が必要ですが、その分成長を楽しむことができます。
この記事が、蝋梅の花と香りを楽しむための参考になれば嬉しいです。