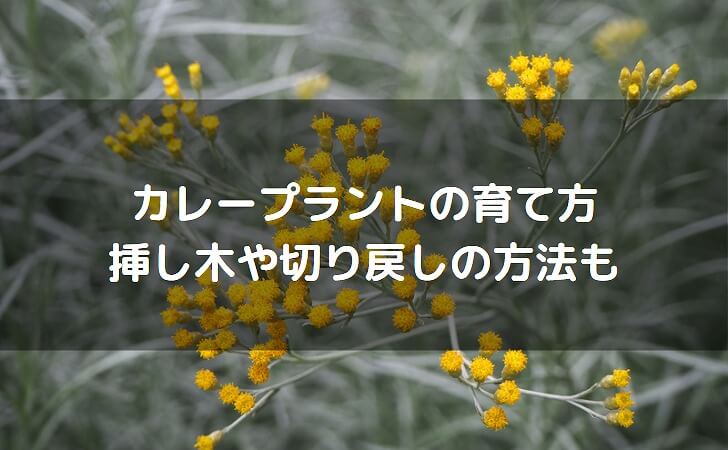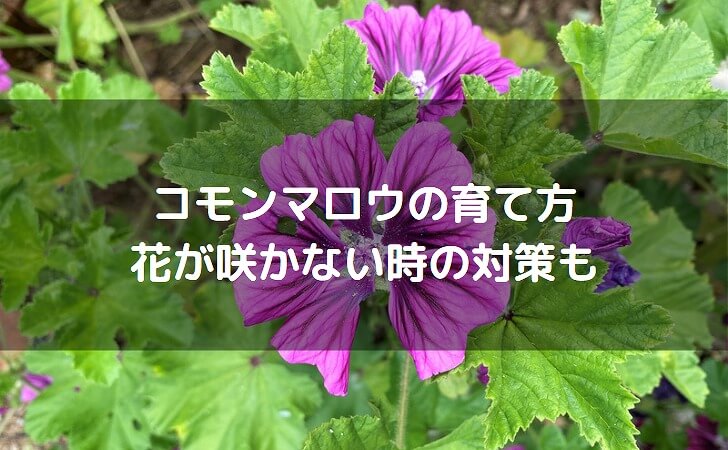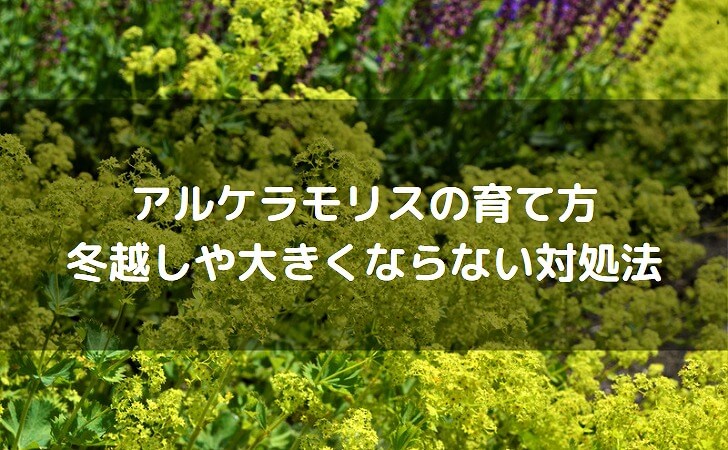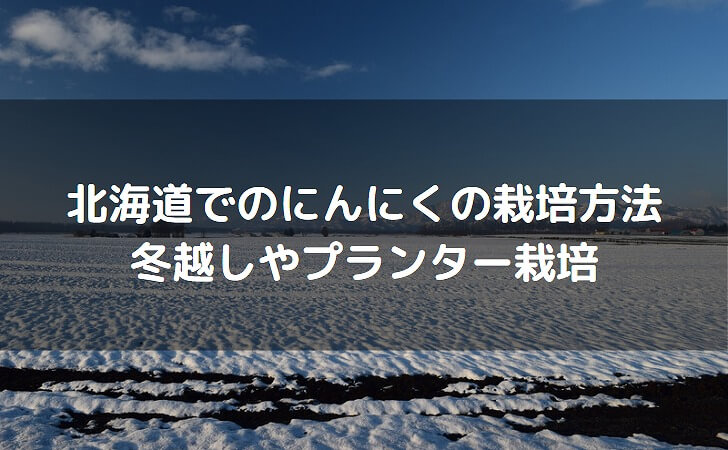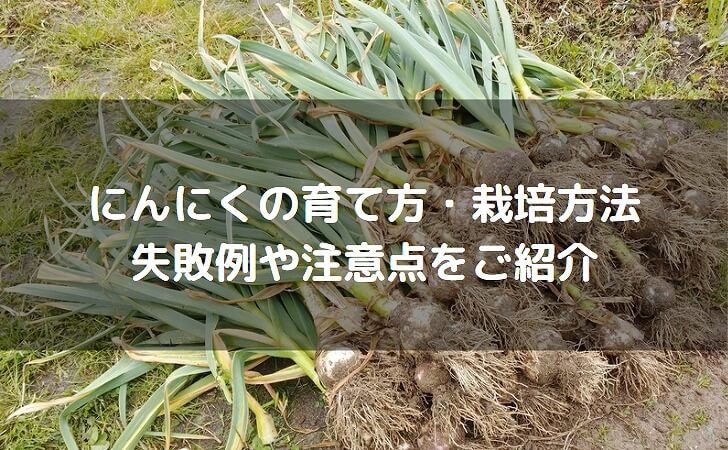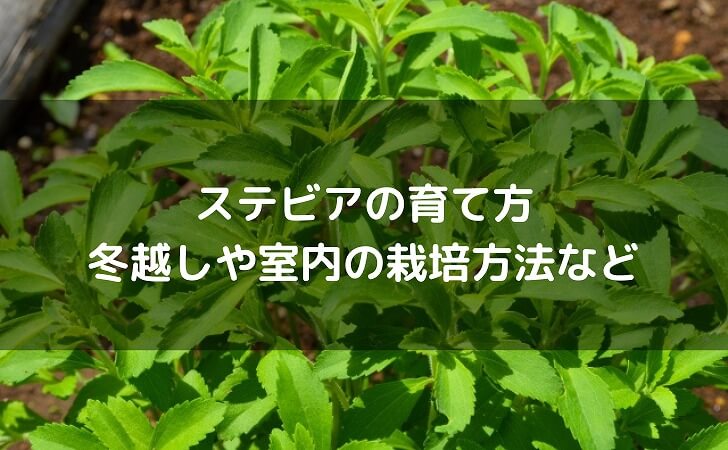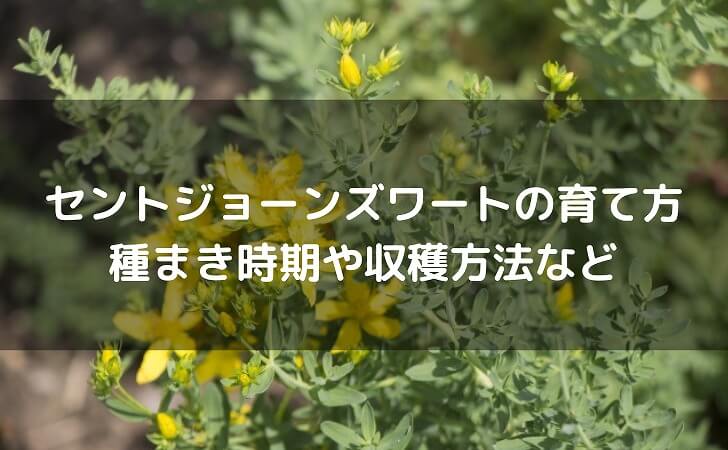カレープラント(学名: Helichrysum italicum)はカレーのような香りがするハーブの仲間で、銀色の細い葉と黄色い小さな花をつける南ヨーロッパ原産の多年草です。
ちょっと変わったハーブなので育ててみたいと思っても、カレープラントの育て方や注意点の情報が足りないと感じている方も多いと思います。
この記事では、カレープラントの地植えや鉢植え方法などの基本的な情報から、挿し木や切り戻しの方法など、幅広くご紹介しています。
カレープラントの甘くフルーティーな香りは精神安定や疲労回復にも役立ちますし、料理の香りづけやドライフラワーやポプリなどにも使えるハーブなので、ぜひご家庭でも育ててみてくださいね。
カレープラントの種まき時期と方法
カレープラントの種の発芽条件は気温が15度以上なので、種まき時期は春から夏にかけて行うのが適しています。
種は小さくて細かいため発芽率が低いので、他の植物と比べて少し多めにまくことをおすすめします。
カレープラントの種まき方法は、
- 土に直接まく方法
- ポットにまく方法
の2通りがあります。それぞれのメリットや注意点をお伝えします。
土に直接まく方法
土に直接まくというのは、庭の畑やプランターなどに種をまくことを指します。
この方法のメリットは移植の手間が省けることです。注意点としては土が乾燥しないように水やりをすることと、雑草や害虫に注意することが挙げられます。
土に直接まく方法の手順は以下のとおりです。
- 土をほぐし、水はけの良い状態にする。
- 種を均等にまく。深く埋めないように注意する。
- 種を軽く押さえて固定する。
- 水やりをして湿らせる。
- 日当たりの良い場所に置く。
次に、カレープラントの種をポットにまく方法についてご紹介します。
ポットにまく方法
ポットにまくというのは、小さな鉢やトレイなどに種をまくことを指します。
この方法のメリットは発芽率が高くなることと、管理がしやすいことです。注意点としては発芽後に移植する必要があることと、ポットが乾燥しないように水やりをすることが挙げられます。
ポットにまく方法の手順は以下のとおりです。
- ポットに軽石や赤玉土などの排水材を敷く。
- ポット用土を入れる。
- 種を均等にまく。深く埋めないように注意する。
- 種を軽く押さえて固定する。
- 水やりをして湿らせる。
- ビニール袋などで覆って温室効果を作る。
- 日当たりの良い場所に置く。
どちらの方法でも種まきは可能ですが、メリットと注意点を比較して種まきの方法を検討してみてくださいね。
なお、カレープラントが発芽したら、本葉が2~3枚出た頃に元気な芽を残すように間引きします。
間引いた苗は別の場所に移植できますが、移植する場合は根が傷まないように注意しましょう。
カレープラント栽培の環境(用土づくり・水やりと肥料の与え方)
種蒔きをした後は、カレープラントの栽培に適した環境づくりを行います。
カレープラント栽培には日当たり良い場所が適しています。その他、用土づくり・水やり・肥料の与え方のポイントを次にご紹介します。
【用土づくり】
カレープラントは水はけの良い用土を好むので、市販のハーブ用土やポット用土を使う場合は、軽石や赤玉土などの排水材を混ぜると良いでしょう。
自分で用土を作る場合は、赤玉土と腐葉土と砂を3:2:1の割合で混ぜるのが望ましいです。
pHは酸性から中性が適しています。
【水やり】
カレープラントは乾燥に強い植物ですが水不足になると葉がしおれてしまうため、水やりは土が乾いたら行うようにします。その際、過湿にならないように注意しましょう。
水やりの頻度は、夏場は毎日、冬場は2~3日に1回程度を目安として、朝か夕方に行います。
【肥料の与え方】
肥料は月に1~2回、液体肥料や有機肥料などを適量与えましょう。
タイミングとしては、水やりの後に与えるのが望ましいです。肥料を与えすぎると香りが弱くなることがあるのでご注意ください。
カレープラントの苗の地植え(畑へ植え付ける)方法
カレープラントはポットで育てることもできますが、畑に植え付けることでより大きく育てることができます。
カレープラントの苗の地植えは、春から秋にかけて行うことができます。苗の地植えの手順は次のとおりです。
| No. | 手順 | ポイント |
| 1 | 苗を慣らす | 地植えする前に外気に慣らす必要があるので、ポットに入ったまま日当たりの良い場所に置きます。最初は数時間から始めて、徐々に時間を長くしていきましょう。 |
| 2 | 苗をポットから抜く | ポットから苗を抜く際は根が傷まないように注意しましょう。根が張り付いている場合は、ポットを軽く叩いて外すようにします。 |
| 3 | 土をほぐす | カレープラントは根が深く伸びる植物なので、土を深く耕してほぐしましょう。土が固い場合は、軽石や赤玉土などの排水材を混ぜると良いです。 |
| 4 | 穴を掘る | 穴は苗と同じくらいの大きさにし、穴の間隔は30~40cm程度空けるようにします。 |
| 5 | 苗を植える | 根本が埋まらないように注意しながら穴に苗を入れて土で固定します。 |
| 6 | 水やりをする | 苗を植えたらたっぷりと水やりをしましょう。水やりは根元に直接行うようにします。 |
カレープラントを鉢植え・プランターで育てる方法
カレープラントは鉢植えやプランターで育てることもできます。
鉢植えやプランターで育てる場合は、鉢植え・プランター選びが適切であれば、地植えと同じように行えば問題ありません。
ここでは、カレープラント栽培時の鉢植えやプランターの選び方についてお伝えします。
【鉢植え・プランターの選び方】
カレープラントを鉢植えやプランターで育てる場合は、以下のような点に注意して選びましょう。
| 注意箇所 | 注意点 |
| サイズ | カレープラントは根が深く伸びる植物なので、深さがあるものを選びましょう。直径は15~20cm程度が目安です。 |
| 素材 | 水はけの良い環境を好むので、鉢やプランターは陶器やテラコッタなどの素焼きのものを選びましょう。プラスチックや金属などのものは水分を保持しすぎて蒸れることがあるので、使用する際は水やりに特に注意が必要となります。 |
| 穴 | カレープラントは過湿になると根腐れの原因になるため、鉢やプランターには底に穴があるものを選びましょう。穴がない場合は自分で開けるか、鉢皿に石や砂などを敷いて高さをつけましょう。 |
カレープラントの植え替え方法
カレープラントは鉢植えやプランターで育てる場合、定期的に植え替えることが必要です。植え替えることで、根の成長や土の状態を整えることができます。
ここでは、カレープラントの植え替え方法について紹介します。
【植え替えの時期】
カレープラントの植え替えの時期は、春から秋にかけてです。特に春は新芽が出る前に行うのが望ましいです。
冬は休眠期に入るので、植え替えは避けましょう。
植え替えの目安は、根が鉢からはみ出してきたり、土が固まってきたりしたら行うようにします。
【植え替えの手順】
カレープラントの植え替えの手順は以下のとおりです。
- 鉢を用意する
- 用土を用意する
- 苗を抜く
- 根を整理する
- 鉢に植える
- 水やりをする
カレープラントの植え替えには、新しい鉢・新しい用土を用意します。鉢は深さがあるものを選びましょう。
苗を抜く際には古い鉢から抜きます。根が傷まないように注意しましょう。根が張り付いている場合は、鉢を軽く叩くと外れやすくなります。
根の整理は古い土や枯れた根を取り除くようにします。根が長くなっている場合は、やや切り詰めると良いでしょう。
カレープラントの剪定・切り戻しの時期と方法
カレープラントは定期的に剪定や切り戻しをすることで、枝分かれを促し、より茂りやすくなります。
また、剪定や切り戻しをすることで、葉の香りも強くなります。
ここでは、カレープラントの剪定や切り戻しの時期と方法について紹介します。
【剪定・切り戻しの時期】
カレープラントの剪定や切り戻しの時期は、春から秋にかけてです。特に春は新芽が出る前に行うのが良いです。
冬は休眠期に入るので、剪定や切り戻しは避けましょう。
剪定や切り戻しの目安は、枝が伸びすぎたり葉が茂りすぎたりしたら行うようにします。
【剪定・切り戻しの方法とポイント】
カレープラントの剪定や切り戻しの方法とポイントは以下のとおりです。
| 作業 | 方法 | 効果 |
| 剪定 | 枝先を摘み取る | 枝分かれを促し、より茂りやすくなる。摘み取った葉は料理やお茶に使える。 |
| 切り戻し | 枝を半分くらいに切る | 新芽が出やすくなり葉の香りも強くなる。切った枝は水挿しや挿し木にして増やせる。 |
カレープラントの増やし方
カレープラントの増やし方としては、以下の3つが挙げられます。
- 挿し木で増やす方法
- 株分けで増やす方法
- 葉挿しで増やす方法
それぞれの方法について、詳しくお伝えしていきます。
挿し木で増やす方法
カレープラントの挿し木は、春から秋にかけて行うのが適しています。
挿し木の手順は以下のとおりです。
| No. | 方法 | ポイント |
| 1 | 枝を切る | カレープラントの枝を10~15cmくらいに切ります。切るときは、節の上から2~3cmくらいのところで切りましょう。 |
| 2 | 葉を取る | 切った枝の下半分の葉を取ります。葉が多すぎると水分が失われやすくなります。 |
| 3 | 水に浸けるか土に挿す | 切った枝を水に浸けるか土に挿します。水に浸ける場合は、透明な容器に水を入れて枝を入れます。土に挿す場合は、排水材と用土を混ぜた鉢に枝を挿します。 |
| 4 | に当たりの良い場所に置く | 水に浸けた場合は、日当たりの良い場所に置きます。土に挿した場合は、日陰の場所に置きます。 |
| 5 | 根が出るまで管理する | 水に浸けた場合は水が汚れたら取り替えます。土に挿した場合は土が乾いたら水やりをします。根が出るまで約1ヶ月程度かかります。 |
株分けで増やす方法
カレープラントの株分けは、春か秋に行うのが適しています。
株分けの手順は以下のとおりです。
| No. | 方法 | ポイント |
| 1 | 苗を抜く | カレープラントの苗を鉢から抜きます。根が傷まないように注意しましょう。 |
| 2 | 根茎を分割する | カレープラントの根茎を2~3個ずつに分割します。分割するときは、根茎が傷まないように注意しましょう。 |
| 3 | 鉢に植え付ける | 新しい鉢に排水材と用土を入れます。根茎を入れて土で固定しましょう。 |
| 4 | 水やりをする | 植え付けたらたっぷりと水やりをしましょう。水やりは根元に直接行いましょう。 |
葉挿しで増やす方法
カレープラントの葉挿しは、春から秋にかけて行うのが適しています。
葉挿しの手順は以下のとおりです。
| No. | 方法 | ポイント |
| 1 | 葉を切る | カレープラントの葉を2~3枚ずつ切ります。切るときは、葉柄も一緒に切りましょう。 |
| 2 | 水に浸けるか土に挿す | 切った葉を水に浸けるか土に挿します。水に浸ける場合は、透明な容器に水を入れて葉柄を入れます。土に挿す場合は、排水材と用土を混ぜた鉢に葉柄を挿します。 |
| 3 | 日当たりの良い場所に置く | 水に浸けた場合は、日当たりの良い場所に置きます。土に挿した場合は、日陰の場所に置きます。 |
| 4 | 根が出るまで管理する | 水に浸けた場合は、水が汚れたら取り替えます。土に挿した場合は、土が乾いたら水やりをします。根が出るまで約1ヶ月程度かかります。 |
カレープラントの収穫時期と方法
カレープラントは葉や花が食用になるハーブです。
カレープラントの収穫は春から秋にかけて行うことができますが、花は開花時期の夏に収穫します。
葉が茂ったり、花が咲いたりしたら行うくらいを目安にするのが良いでしょう。
カレープラントの収穫の方法は以下のとおりです。
| 収穫物 | 収穫方法 |
| 葉の収穫 | 葉は枝先を摘み取ることで収穫できます。摘み取ることで枝分かれを促し、より茂りやすくなります。摘み取った葉は料理やお茶に使えます。 |
| 花の収穫 | 花は花が咲いたら摘み取ることで収穫できます。摘み取ることで葉の成長を促し、より香り高くなります。摘み取った花は料理やお茶に使えます。 |
収穫後の保存方法
葉や花は新鮮なうちに使うと香りが良いです。保存する場合は以下のような方法があります。
| 保存の手順 | 補足 |
| 乾燥させる | 葉や花を束ねて風通しの良い場所で陰干しする。完全に乾燥したら密閉容器に入れて冷暗所で保存する。 |
| 冷凍保存する | 葉や花を洗って水気を切り、ジップロックなどに入れて冷凍庫で保存する。 |
| オイル漬けにする | 葉や花を洗って水気を切り、オリーブオイルなどと一緒に瓶に入れて保存する。 |
上記により、カレープラントを保存して必要な時に使えるようにできます。
カレープラントの夏越しのやり方と注意点
カレープラントは暖かい気候を好むハーブですが、夏や冬にも注意して管理する必要があります。
カレープラントの夏越しは、以下の点に注意して行いましょう。
| 作業 | ポイント |
| 水やり | 夏は暑く乾燥することが多いので、水やりをこまめに行いましょう。土が乾いたらたっぷりと与えます。時間帯は朝か夕方が適しています。 |
| 日陰づくり | 日差しが強すぎると葉が焼けてしまうことがあるため、日差しが強すぎる場合は日陰を作ってあげましょう。日陰はカーテンやシートなどで作ることができます。 |
| 虫除け | カレープラントは虫除け効果があるハーブですが、完全に防ぐことはできません。害虫が発生した場合は手で取り除くか、水や石鹸水などで洗い流すか、天然の殺虫剤を使って対処しましょう。 |
カレープラントの冬越しのやり方と注意点
カレープラントの冬越しは、以下の点に注意して行いましょう。
| 作業 | ポイント |
| 水やり | 冬は寒く乾燥することが多いのでたまに確認をし、土が乾いたら少量の水やりをしましょう。水やりは昼間に行うのが適しています。 |
| 防寒対策 | カレープラントは耐寒性が低いので、霜や雪に当たらないように注意が必要です。霜や雪が降る場合は、鉢を屋内に移動させるか、ビニール袋などで覆って保温しましょう。 |
| 休眠期の扱い | 冬は休眠期に入ることがあり、葉が枯れて落ちることがあります。これは自然な現象なので心配無用で、春になると新芽が出てきます。 |
カレープランツの寄せ植えの方法とコツ
カレープランツの寄せ植えの方法は以下のとおりです。
| No. | 寄せ植えの手順 | ポイント |
| 1 | 鉢を用意する | カレープランツの寄せ植えには、深さがある鉢を用意します。鉢は素焼きのものがおすすめです。鉢には底に穴があるものを選びましょう。 |
| 2 | 用土を準備する | 地植え・鉢植えの際と同じ要領で構いません。 |
| 3 | 植物を選ぶ | 日当たりと水はけの好みが似ている植物を選ぶと育てやすい。 |
| 4 | 植え付ける | 鉢に排水材と用土を入れ、カレープランツを中心に他の植物を配置する。 |
| 5 | 水やりをする | 植え付けたら根元にたっぷりと水やりをする。 |
カレーリーフの寄せ植えをするコツとしては、一緒に寄せ植えをする植物選びは外せません。
日当たりと水はけの好みが似ている植物としてハーブの中で選ぶなら、ローズマリー、ラベンダー、タイム、マリーゴールドなどがおすすめです。
植え付ける際には高さや色や形などをバランスよく整えることを意識し、小石や貝殻や木片などで飾り付けすると見栄えが更に良くなります。
適宜、枝先を摘み取ることで剪定を行いますが、摘み取ることで枝分かれを促してより茂りやすくなります。
カレープラントの育て方に関するQ&A
ここでは、カレープラントの育て方に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。
- カレープラントに耐寒性はある?
- カレープラントは多年草?枯れることはあるか
- カレープラントは北海道で栽培できる?
- カレープランツ栽培で気をつけるべき病害虫は?
- カレープラントはずっとカレーの匂いがするハーブなの?
- カレープラントは虫除けに使えるって本当?
上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。
カレープラントに耐寒性はある?
カレープラントは暖かい気候を好むハーブですが、ある程度の耐寒性があり-5℃程度までなら大丈夫です。
ただし、霜や雪に当たると枯れてしまうことがあるので、冬は鉢を屋内に移動させるか、ビニール袋などで覆って保温するなどの防寒対策は欠かせません。
カレープラントが枯れる主な原因は?
カレープラントは育てやすいハーブですが、枯れてしまうこともあります。カレープラントが枯れる主な原因は、以下のようなものが考えられます。
| 枯れる原因 | 説明 |
| 水やりが不適切 | 水やりのしすぎは蒸れて根腐れの原因になりますが、逆に水やりのし足りなさは葉がしおれる原因になります。 |
| 日当たり量が不適切 | 日当たりの不足は葉が黄色くなる原因になりますが、逆に日当たりの過剰は葉が焼ける原因になります。 |
| 肥料の量が足りない | 肥料が足りないと成長が悪くなる原因になり、最悪の場合枯れてしまいます。 |
| 霜や雪への対策不足 | 寒さに強いハーブではないので、霜や雪に当たると枯れてしまうことがあります。 |
カレープラントは北海道で栽培できる?
カレープラントは暖かい気候を好むハーブですが、しっかりと対策をすれば北海道でも栽培できることがあります。
カレープラントは北海道で栽培する場合、以下のような点に注意して行いましょう。
| 対処法 | 説明 |
| 鉢植えにする | 北海道では地植えにすると冬に枯れてしまいやすいので、鉢植えにそて屋内に移動させるようにします。 |
| 防寒対策をする | 鉢を屋内に移動させるか、ビニール袋などで覆って保温すると良いでしょう。 |
| 水やりを控える | 冬の休眠期に入ったら水やりを控えます。 |
カレープランツ栽培で気をつけるべき病害虫は?
カレープランツは虫除け効果があるハーブですが、病害虫に完全に免疫があるわけではありません。
カレープランツ栽培で気をつけるべき病害虫は、以下のようなものです。
| 主な病害虫 | 説明 |
| アブラムシ | 吸汁することで葉がしおれたり、ウイルス病を媒介したりします。アブラムシが発生した場合は、手で取り除くか、水や石鹸水などで洗い流すか、天然の殺虫剤を使って対処しましょう。 |
| ハダニ | 吸汁することで葉に白い斑点ができたり、枯れたりします。ハダニが発生した場合は、水や石鹸水などで洗い流すか、天然の殺虫剤を使って対処しましょう。 |
| 根腐れ | 水やりのしすぎや過湿が原因になります。根腐れが発生した場合は、根を切り取って健康な部分だけ残すか、新しい鉢に植え替えるかして対処しましょう。 |
カレープラントはずっとカレーの匂いがするハーブなの?
カレープラントは葉や花がカレーのような香りがするハーブです。しかし、カレープラントはずっとカレーの匂いがするわけではありません。
カレープラントの香りは、以下のような要因によって変化します。
| 要因 | 匂いの変化 |
| 気温 | 気温が高いときは香りが強くなり、気温が低いときは香りが弱くなる。 |
| 摘み取り | カレープラントの香りは摘み取ることで葉や花から香り成分が放出される。 |
| 肥料 | 肥料を与えることで葉や花の成長を促しますが、肥料を与えすぎると香りが弱くなることがある。 |
カレープラントは虫除けに使えるって本当?
カレープラントの葉や花から出るカレーのような香りは人間には心地よいですが、一部の虫にとっては嫌な匂いです。
そのため、ハエや蚊やアブラムシなどの小さな虫を遠ざけることは可能ですが、カレープラントの香りに慣れてしまった虫や強い刺激に耐えられる虫に対してはほとんど効果はありません。
結論としては、カレープラントだけで完全に虫を防ぐことはできず、あくまで補助的な効果として用いる程度にしかならないので、カレープラントを虫除け対策用として栽培するのであれば、期待ほどの効果は得られないでしょう。
まとめ:カレープラントの育て方と増やし方
カレープラントはカレーのような香りがするハーブで、ドライフラワーやスパイスとしても使えます。
日当たりと風通しの良い場所で乾燥気味に育てるのがポイントなので、水はけの良い土を用意し、春か秋に苗を植え付けます。
生育期間中はこまめに剪定し、梅雨や夏は過湿や直射日光を避け、冬は軽い霜程度なら耐えられますが、強い霜には注意しましょう。
挿し木で増やす場合は、春から夏にかけて切った枝を水揚げして挿します。
株分けや葉挿しでも増やすことができるので、一番やりやすい方法を選んで増やしてみてくださいね。
カレープラントが好きな方は、カレーリーフもおすすめです!
カレーリーフの育て方についてはこちらのページでお伝えしています。
[surfing_other_article id=”305″]