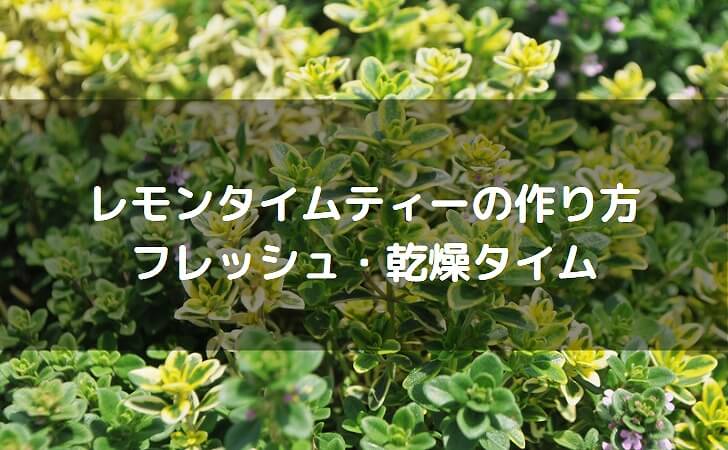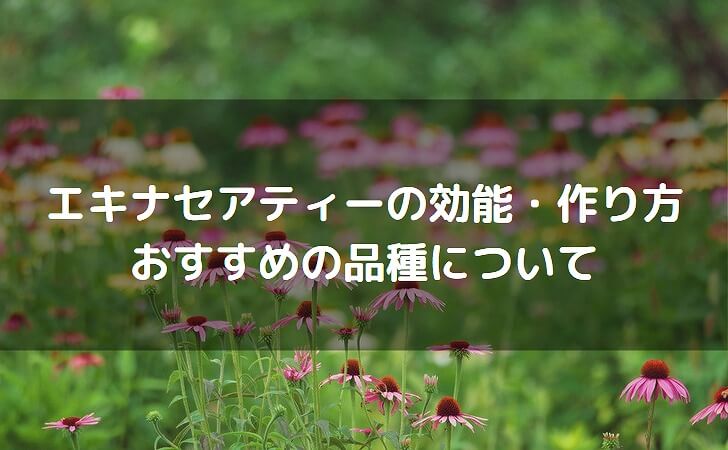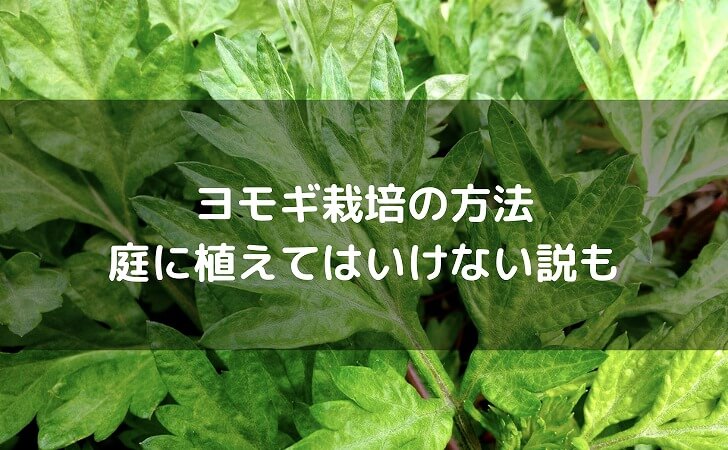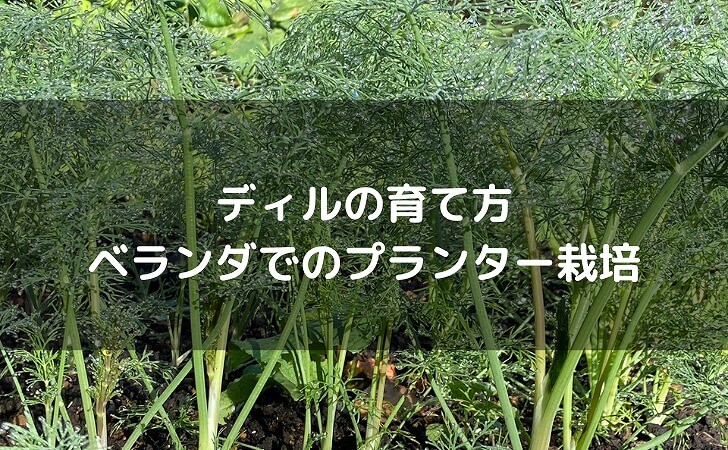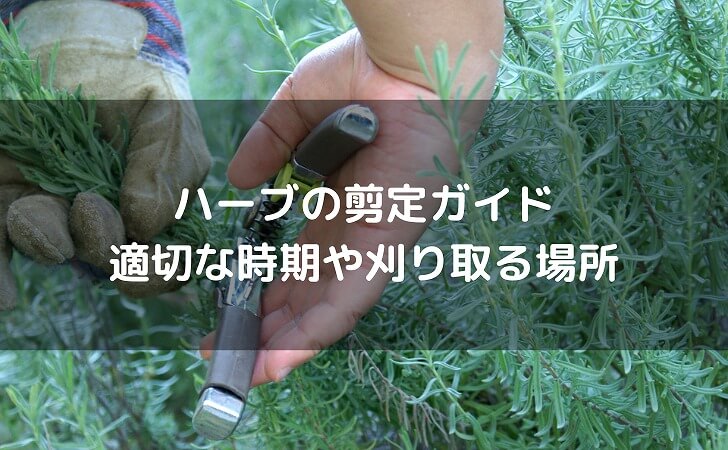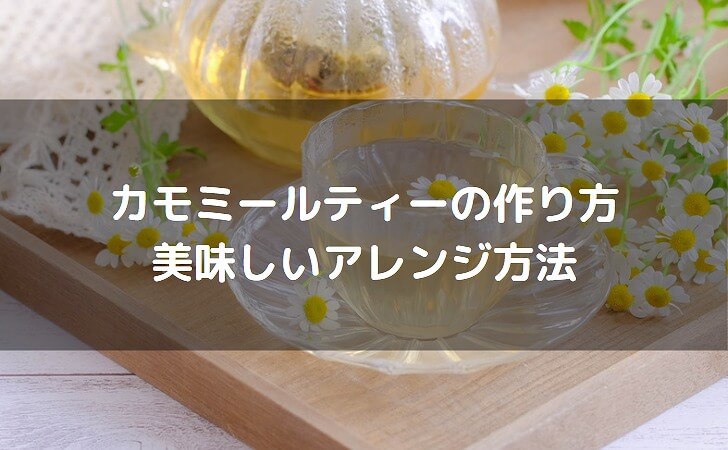カモミールティーは香りも良くて飲みやすいので、日常的に楽しむことができるハーブティーですが、カモミールティーの作り方や飲み方を正しく知っている人は少ないかもしれません。
カモミールの生花を使って自家製のカモミールティーを作ることは簡単ですが、既製品のカモミールティーしか飲んだことがないという人は多いでしょう。
この記事では、カモミールティーの作り方や美味しい飲み方のアレンジについて詳しくご紹介します。
カモミールティーの効能を最大限に引き出すために、ぜひ参考にしてください。
[surfing_other_article id=”2702″]
簡単にできる!カモミールティーの作り方
カモミールティーは市販のティーバッグやドライカモミールを使って簡単に作ることができますが、自分で育てたカモミールの花を使って手作りすると、より香り高くて美味しいカモミールティーを楽しむことができます。
カモミールの花は5月から6月にかけてが花期です。収穫時は花だけを摘むときれいに乾燥できます。
今回は、手作りカモミールティーの作り方をご紹介します。
【材料】(2人分)
- カモミールの花(乾燥させたもの) 大さじ2杯
- お湯 400ml
【作り方】
- カモミールの花を収穫する。
- カモミールの花を水洗いして水気を切る。
- キッチンペーパーを敷いたザルに広げて2~3日ほど天日干しする。
- カラカラに乾いたら乾燥剤を入れた密閉容器に入れて保存する。
- ポットやティーポットに乾燥させたカモミールの花を入れて、沸騰したお湯を注ぐ。
- 5分から10分ほど蒸らしてから、茶こしで濾してカップに注ぐ。
- お好みではちみつやレモンなどを加える。
手作りカモミールティーは自然な香りと味が楽しめるだけでなく、自分で育てたカモミールの花を使うことで愛着も感じられる素敵な飲み物です。ぜひ挑戦してみてくださいね。
生花を使ったフレッシュカモミールティーの作り方
カモミールティーは乾燥させた花を使って淹れるのが一般的ですが、生花を使って淹れるとよりフレッシュで爽やかな香りと味が楽しめます。生花を使ったフレッシュカモミールティーの作り方はとても簡単です。
今回は、生花を使ったフレッシュカモミールティーの作り方をご紹介します。
【材料】(2人分)
・カモミールの花(新鮮なもの) 10個
・お湯 400ml
【作り方】
- カモミールの花を収穫する。(花びらが反っていない、中心が盛り上がっている花が良い)
- 虫や汚れが付いていないか確認して、水でよく洗う。
- ポットやティーポットにカモミールの花を入れて、沸騰したお湯を注ぐ。
- 3分から5分ほど蒸らしてから茶こしで濾してカップに注ぐ。
- お好みではちみつやレモンなどを加える。
生花を使ったフレッシュカモミールティーは、乾燥させたものよりも香りが強くて甘みがあります。自分で育てたカモミールの花を使うと、より新鮮で美味しいカモミールティーを楽しむことができます。ぜひ挑戦してみてくださいね。
カモミールティーはどんな味がするのか
カモミールティーの味は人によって感じ方が異なりますが、一般的にはリンゴのような甘さや爽やかな味と表現されることが多いです。
それと同時に、タンニンと呼ばれる成分による苦みや渋みが感じられることもあります。また、リンゴやパイナップルのような甘い香りも特徴的です。
上記のような特徴があるカモミールティーの味は、淹れ方によっても変わります。苦みや渋みを抑えたい場合は、低温のお湯で淹れたり抽出時間を短めにしたりすると良いでしょう。
また、はちみつやレモンなどを加えると甘みや酸味が加わって飲みやすくなります。
さらにカモミールティーは他のハーブとブレンドすることもできます。おすすめのブレンド例は下記のとおりです。
| ブレンド例 |
味の変化 |
| ペパーミント |
爽快な風味が加わり、さわやかな味に変化します。 |
| 紅茶 |
コクと香りが増してまろやかな味に変化します。 |
| ハイビスカスやローズヒップ |
鮮やかな色になり、酸味の加わったフルーティーな味に変化します。 |
カモミールティーは自分好みの味に調整して飲むことができる万能なハーブティーです。香りだけでなく、優しい味わいも楽しんでくださいね。
ローマンカモミールティーの作り方
ローマンカモミールティーの作り方はとても簡単で、ドライハーブを使ってお湯で淹れるだけです。ここではローマンカモミールティーの作り方と、おすすめの飲み方をご紹介します。
【ドライハーブを使う場合】
- ティーポットにドライハーブを小さじ1杯分を入れます。
- 沸騰した熱湯を注ぎいれたらフタをして約3分蒸らします。
- 蒸らし時間が終わったら茶こしでこしてティーカップに注ぎます。
- お好みで、はちみつやレモンなどを加えてお楽しみください。
【生の花を使う場合】
- 収穫したローマンカモミールの花は、水洗いしてよく水気を切ります。
- ティーポットに生の花を10~15個ほど入れます。
- 沸騰した熱湯を注ぎいれたらフタをして約5分蒸らします。
- 蒸らし時間が終わったら茶こしでこしてティーカップに注ぎます。
- お好みではちみつやレモンなどを加えてお楽しみください。
ローマンカモミールティーのおすすめの飲み方
就寝前に飲む
ローマンカモミールティーにはリラックス効果や睡眠促進効果があります。就寝前に飲むと、心身ともに落ち着いて眠りにつきやすくなります。カフェインが含まれていないので安心して飲めます。
食後に飲む
ローマンカモミールティーには消化促進効果や胃腸の調子を整える効果があります。食後に飲むと、食べ過ぎや胃もたれなどの不快感を和らげてくれます。また、利尿作用もあるのでむくみや便秘の予防にも役立ちます。
冷やして飲む
ローマンカモミールティーは冷やしても美味しく飲めます。暑い日や喉が渇いた時には冷蔵庫で冷やしたローマンカモミールティーを飲むと、さっぱりとした味わいで爽やかになります。氷を入れてアイスティーにしてもおいしいですよ。
カモミールティーはまずい?おすすめのアレンジレシピ
カモミールティーは、甘くて爽やかな味ですが、まずいと感じる方は少なくないようです。
苦みや渋みが苦手な方もいるかもしれませんし、同じ味に飽きてしまうこともありますよね。
そんなときは、カモミールティーをアレンジして違った味わいを楽しんでみましょう。ここでは、おすすめのカモミールティーのアレンジレシピをご紹介します。
【はちみつとレモンを加える】
カモミールティーにはちみつとレモンを加えると、甘酸っぱくて爽やかな味になります。はちみつには殺菌効果や喉の保湿効果があり1、レモンにはビタミンCが豊富に含まれています。風邪のひき始めや喉の痛みにも効果的です。冷やしてアイスティーにしても美味しいですよ。
【ミルクを加える】
カモミールティーにミルクを加えると、コクと香りが増してまろやかな味になります。カフェインが入っていないので、就寝前に飲んでも安心です2。お砂糖やはちみつで甘みを調整してください。牛乳の代わりに豆乳やアーモンドミルクを使っても美味しくできます。
【フルーツを加える】
カモミールティーにフルーツを加えると、色鮮やかでフルーティーな味わいが楽しめます。オレンジやグレープフルーツ、イチゴやブルーベリーなど、好きなフルーツをカットしてカモミールティーに浮かべてください1。冷蔵庫で冷やしてから飲むとさらに美味しいです。
【白コショウを加える】
カモミールティーに白コショウを少量加えると、ピリッとした刺激が加わって飲みごたえが増します。白コショウには血行促進や発汗作用があるので1、体を温めたい時におすすめです。ただし、辛さが苦手な方は注意してください。
【カルピスと合わせる】
カモミールティーにカルピスを合わせると、甘酸っぱくてさっぱりした味になります。カルピスには乳酸菌が含まれているので1、胃腸の調子を整える効果が期待できます。水ではなくカモミールティーで割って飲んでみてください。
以上、おすすめのカモミールティーのアレンジレシピでした。カモミールティーは、自分好みの味にアレンジして飲むことができます。香りだけでなく、味も楽しんでくださいね。
オレンジカモミールティーの作り方
オレンジカモミールティーの作り方はとても簡単で、ドライハーブとオレンジジュースを使ってお湯で淹れるだけです。
ここではオレンジカモミールティーの作り方と、おすすめの飲み方をご紹介します。
【ドライハーブとオレンジジュースを使う場合】
- ティーポットにドライハーブを小さじ1杯分を入れる。
- 沸騰した熱湯を注ぎいれたらフタをして約3分蒸らす。
- 蒸らし時間が終わったら、茶こしでこしてティーカップに注ぐ。
- オレンジジュースをお好みの量加えて混ぜる。
- お好みで、はちみつやレモンなどを加える。
【生の花とオレンジ果汁を使う場合】
- 収穫したローマンカモミールの花は水洗いしてよく水気を切る。
- ティーポットに生の花を10~15個ほど入れる。
- 沸騰した熱湯を注ぎいれたら、フタをして約5分蒸らす。
- 蒸らし時間が終わったら、茶こしでこしてティーカップに注ぐ。
- オレンジを半分に切って果汁をしぼり、お好みの量加えて混ぜる。
上記の作り方で美味しいオレンジカモミールティーは作れますが、美味しく飲めるおすすめの方法も併せてご紹介します。
【ホットで飲む】
オレンジカモミールティーは温かいまま飲むと、カモミールの香りとオレンジの甘酸っぱさが口いっぱいに広がります。
リラックス効果や身体を温める効果もあり、就寝前や寒い日に飲むと心身ともに癒されるでしょう。
【アイスで飲む】
オレンジカモミールティーは冷やしても美味しく飲めます。
暑い日や喉が渇いた時には冷蔵庫で冷やしたオレンジカモミールティーを飲むと、さっぱりとした味わいで爽やかになります。氷を入れてアイスティーにしてもおいしいですよ。
【シロップでアレンジする】
オレンジカモミールティーはシロップを加えることで、さらに風味豊かになります。オレンジのシロップを作る方法は、100%のオレンジジュースとガムシロップを1:1で混ぜ合わせるだけです。
オレンジカモミールティーにお好みの量を加えて混ぜ合わせましょう。他にもメープルシロップやハチミツなどもおすすめです。
カモミールティーラテ(ミルクティー)の作り方
カモミールティーラテの作り方はとても簡単で、ドライハーブと牛乳を使ってお湯で淹れるだけです。ここではカモミールティーラテの作り方と、おすすめの飲み方をご紹介します。
【ドライハーブと牛乳を使う場合】
- ティーポットにドライハーブを小さじ1杯分を入れる。
- 沸騰した熱湯を注ぎいれたらフタをして約5分蒸らす。
- 小鍋に牛乳を入れて温める。
- 蒸らし時間が終わったら茶こしでこしてティーカップに注ぐ。
- 温めた牛乳をお好みの量加えて混ぜる。
- お好みで、はちみつやシナモンなどを加える。
【ティーバッグと牛乳を使う場合】
- マグカップにカモミールのティーバッグを入れる。
- 沸騰した熱湯を注ぎいれたらフタをして約3分蒸らす。
- 小鍋に牛乳を入れて温める。
- 蒸らし時間が終わったらティーバッグを取り出す。
- 温めた牛乳をお好みの量加えて混ぜる。
- お好みで、はちみつやシナモンなどを加える。
上記の作り方で美味しいカモミールティーラテは作れますが、美味しく飲めるおすすめの方法も併せてご紹介します。
ホットで飲む
カモミールティーラテは温かいまま飲むと、カモミールの香りと牛乳のまろやかさが口いっぱいに広がります。リラックス効果や身体を温める効果もあります。就寝前や寒い日に飲むと心身ともに癒されます。
アイスで飲む
カモミールティーラテは冷やしても美味しく飲めます。暑い日や喉が渇いた時には冷蔵庫で冷やしたカモミールティーラテを飲むと、さっぱりとした味わいで爽やかになります。氷を入れてアイスティーにしてもおいしいですよ。
フォームミルクでアレンジする
カモミールティーラテはフォームミルクを加えることで、さらに風味豊かになります。フォームミルクを作る方法は、牛乳を温めてからミルクフォーマー等で泡立てるだけです。カモミールティーにお好みの量を加えて混ぜます。見た目も華やかで、カフェ気分を味わえます。
カモミールティーラテは花の香りとミルクのほっとする味だけでなく、リラックス効果や消化促進効果などのさまざまな効果も楽しめる素晴らしいドリンクです。ぜひ、自宅で作ってみてくださいね。
はちみつを使ったカモミールハニーハーブティーの作り方
はちみつを使ったカモミールハニーハーブティーの作り方はとても簡単で、ドライハーブまたはティーバッグとはちみつを使ってお湯で淹れるだけです。
ここでははちみつを使ったカモミールハニーハーブティーの作り方と、おすすめの飲み方をご紹介します。
【ドライハーブとはちみつを使う場合】
- ティーポットにドライハーブを小さじ1杯分を入れます。
- 沸騰した熱湯を注ぎいれたらフタをして約5分蒸らします。
- 蒸らし時間が終わったら茶こしでこしてティーカップに注ぎます。
- お好みの量のはちみつを加えて混ぜます。
【ティーバッグとはちみつを使う場合】
- マグカップにカモミールのティーバッグを入れます。
- 沸騰した熱湯を注ぎいれたらフタをして約3分蒸らします。
- 蒸らし時間が終わったらティーバッグを取り出します。
- お好みの量のはちみつを加えて混ぜます。
上記の作り方で美味しいカモミールハニーハーブティーは作れますが、美味しく飲めるおすすめの方法も併せてご紹介します。
ホットで飲む
はちみつを使ったカモミールハニーハーブティーは温かいまま飲むと、カモミールの香りとはちみつの甘さが口いっぱいに広がります。
リラックス効果や喉の保湿効果もあります。就寝前や風邪気味の時に飲むと、心身ともに癒されるでしょう。
アイスで飲む
はちみつを使ったカモミールハニーハーブティーは、冷やしても美味しく飲めます。
暑い日や喉が渇いた時には冷蔵庫で冷やしたはちみつを使ったカモミールハニーハーブティーを飲むと、さっぱりとした味わいで爽やかになります。氷を入れてアイスティーにしてもおいしいですよ。
レモンを加える
はちみつを使ったカモミールハニーハーブティーにレモン汁を加えると、さらに爽やかな味わいになります。
レモンにはビタミンCやクエン酸が豊富に含まれており、疲労回復や美肌効果も期待できます。風邪の予防や免疫力アップにもおすすめです。
はちみつを使ったカモミールハニーハーブティーはカモミールの花の香りとはちみつの甘い味だけでなく、リラックス効果や喉の保湿効果などさまざまな効果も楽しめる素晴らしいドリンクです。ぜひ、自宅で作ってみてくださいね。
カモミールの葉っぱの乾燥法
カモミールの葉っぱは花と一緒に乾燥させることができます。
乾燥させたカモミールの葉っぱは、ポプリ、入浴剤などに使うことができます。
使い方の詳細については別の記事でご紹介します。(ただいま作成中)
カモミールティーの効能に関するQ&A
ここでは、カモミールティーの効能に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。
- カモミールティーの睡眠効果は?
- カモミールティーはいつ飲めばいいの?
- カモミールティーの効果的な飲み方は?
- カモミールティーに利尿作用はある?
- カモミールティーはむくみ解消に効果がある?
上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。
カモミールティーの睡眠効果は?
カモミールティーは、古代からリラックス効果や安眠効果があるとして愛飲されてきたハーブティーです。
カモミールの睡眠効果が期待される理由には下記の3つがあります。
- フラボノイドという成分により、脳の中で睡眠を誘う物質であるメラトニンの分泌を促進する。
- 神経を鎮める効果や筋肉の緊張を緩和する効果がある。
- 身体が睡眠を必要としているときに、よく眠れるように身体を整える効果がある。
カモミールティーの睡眠効果を高めるためには、寝る前にカップ1杯飲むのがおすすめです。カフェインが入っていないので、夜でも安心して飲めるのはうれしいですね。
ただし、カモミールはキク科の植物なのでキク科アレルギーの方は注意が必要です。また、妊娠中や授乳中の方も過剰摂取は避けましょう。
カモミールティーはいつ飲めばいいの?
カモミールティーは飲むタイミングによって効果も変わってきます。一番おすすめの飲み時は、リラックス効果や安眠効果を感じやすい「就寝前」です。
就寝前にカップ1杯のカモミールティーを飲んでみてください。カモミールに含まれるアピゲニンという成分は、脳内のメラトニンという睡眠ホルモンの分泌を促進し、気分を落ち着かせて質の良い睡眠へと促してくれます。
また、カモミールの優しい香りもリラックス効果を高めてくれます。睡眠不足や不眠に悩んでいる方は、ぜひ試してみてくださいね。
ただし、カフェインが入っていないからといって水分摂取量を増やしすぎると、夜中にトイレに起きてしまうこともあります。その場合は就寝の1~2時間前に飲むようにしましょう。
カモミールティーの効果的な飲み方は?
甘く優しい香りと味わいが楽しめるカモミールティーは、飲み方によってリラックス効果や安眠効果、鎮痛効果や胃腸を整える効果など体への影響も変わってきます。
目的に合わせたカモミールティーの効果的な飲み方をいくつかご紹介します。
| 効果的な飲み方 |
補足事項 |
| 就寝前に飲む |
カモミールティーに含まれるアピゲニンという成分が脳内のメラトニンという睡眠ホルモンの分泌を促進し、気分を落ち着かせて眠りやすくなります。
また、カモミールの優しい香りもリラックス効果を高めてくれます。就寝前にカップ1杯のカモミールティーを飲むことで、質の良い睡眠を得ることができます。睡眠不足や不眠に悩んでいる方はぜひ試してみてくださいね。 |
| ミルクを加える |
カモミールティーに牛乳や豆乳などのミルクを加えると、さらに安眠効果が期待できます。牛乳にはトリプトファンという成分が含まれており、これがセロトニンという神経伝達物質に変化して脳をリラックスさせます。
また、牛乳にはカルシウムも豊富に含まれており、筋肉の緊張を緩和してくれます。 |
| シナモンやジンジャーを加える |
カモミールティーにシナモンやジンジャーなどのスパイスを加えると、冷え性や消化不良に効果的です。
シナモンやジンジャーは血行促進や発汗作用があり、身体を温めて代謝を高めます。また、消化促進や吐き気抑制の効果もあります。カモミールのりんご風の香りにシナモンの甘い香りが加わって、ほっと温まるブレンドです。 |
| レモンやハチミツなどの果物や甘味料を加える |
ビタミンやミネラルを補給できます。 |
以上がカモミールティーの効果的な飲み方の一例です。
カモミールティーはそのままでも美味しく飲めますが、アレンジすることでさまざまな効果を得ることができます。ぜひ、自分の好みや目的に合わせて飲み方を工夫してみてくださいね。
カモミールティーに利尿作用はある?
カモミールティーは利尿作用があると言われています。利尿作用とは、排尿量を増やして体内の水分や老廃物を排出する作用のことです。利尿作用が高まると、むくみの解消やデトックス効果にも繋がります。
一方で、飲み方によっては利尿作用が働きにくくなります。カモミールティーに砂糖や人工甘味料を加えると、利尿作用を妨げる可能性があるため避けるようにしましょう。代わりに、ハチミツの甘さやシナモンの甘い香りなどをプラスしてみてはいかがでしょうか。
甘く優しい香りと味わいのあるカモミールティーはリラックス効果や安眠効果に加えて、利尿作用によってむくみの解消やデトックス効果にも役立ちます。ぜひ、カモミールティーで利尿作用を意識してみてくださいね。
カモミールティーにむくみ解消の効果がある理由とは?
むくみとは体内の水分や老廃物が過剰に溜まってしまうことで、手足や顔などがふくらんだり重だるく感じたりする状態です。
カモミールティーの利尿作用はむくみ解消にも効果があるとお伝えしましたが、そのほかにもカモミールティーにはさまざまなむくみ解消効果があります。
カモミールティーを飲んで血液の循環を良くすることで、むくみの予防にもなります。カモミールティーにむくみ解消効果がある理由について詳しくご紹介します。
発汗作用や血行促進作用があるため
発汗作用と血行促進作用で血液の循環を良くすることによって、むくみ解消の効果が期待できます。さらに、カモミールティーの効果的な飲み方でご紹介したシナモンやジンジャーなどのスパイスを加えると、体を温めて代謝を高める効果がアップしてむくみ解消につながります。
ちなみに、発汗作用には、体温を上げて汗をかくことで体内の余分な水分や老廃物を排出する作用、血行促進作用には、血液の流れを良くして新陳代謝を高める作用があります。
リラックス効果や安眠効果があるため
リラックス効果や安眠効果はむくみ解消にも重要です。なぜならストレスや不眠によって、下記のようなむくみの原因が発生するからです。
- 自律神経のバランスが崩れて交感神経が優位になり、血管が収縮して血液の循環が悪くなる。
- 副腎皮質ホルモンの分泌が過剰に増えることで、水分や塩分の排出を妨げる。
むくみ解消には、カモミールティーを飲んでリラックスしたりよく眠ったりすることが効果的です。自律神経のバランスを整えて、むくみを解消することができます。
カモミールティーの副作用に関するQ&A
ここでは、カモミールティーの副作用に関するQ&A(質問&回答)を紹介します。
- カモミールティーにはカフェインは含まれる?
- 妊娠中でもカモミールティーは飲める?
- カモミールティーの腎臓への影響は?
- カモミールティーを飲み過ぎたらどうなる?
- カモミールティー 1日何杯まで飲める?
上記の問いについて詳しく回答していますので、参考にしてみてくださいね。
カモミールティーにはカフェインは含まれる?
純粋なカモミールティー(原材料がカモミール100%のもの)には、カフェインは含まれていません。そのため、カフェインによって引き起こされる睡眠の質の低下や不安・イライラなどの心配がありません。
一方で、市販されているブレンドされたカモミールティー(原材料に他の茶葉やハーブが混ざっているもの)にはカフェインが含まれている可能性があります。たとえば下記のものがブレンドされたカモミールティーが販売されています。
- 紅茶や緑茶などの茶葉
- ペパーミントやレモングラスなどのハーブ
これらの茶葉やハーブにはカフェインが含まれている可能性があります。カフェインを気にする場合は、市販のカモミールティーの原材料をよく確認して選んでくださいね。
妊娠中でもカモミールティーは飲める?
カモミールティーは妊娠中でも飲めますが、飲み過ぎると以下に挙げるような危険性もあるので注意が必要です。
下記の点に注意して飲み過ぎないようにしましょう。
| 起こりうる危険性 |
補足事項 |
| 子宮収縮作用がある |
子宮収縮作用により妊娠初期や中期に起こると流産や早産のリスクを高める可能性があります。少量であればすぐに影響が出るということはありませんが、念のため妊娠37週以降までは控えた方が良いとされています。もし飲みたい場合は、かかりつけの医師や助産師に相談してください。 |
| カフェインが含まれているものもある |
妊娠中はカフェインやアルコールなどの刺激物質を含む飲み物は控えた方が良いとされています。原材料に茶葉やハーブがブレンドされたカモミールティーは、カフェインが含まれていることがあるため注意してください。 |
カモミールティーは、少量であれば妊娠中に良い効果もあるとされています。たとえば下記の効果が期待できます。
- ストレスや不安を和らげる
- リラックス効果や安眠効果がある
- 便秘やむくみの解消
1度に飲む量はカップ1杯まで、1日に1~2回程度飲むのであれば問題ないとされています。初めのうちは少しずつ飲んで調子を確認する方が安全でしょう。
飲んでみたいと思う方は、事前に医師や専門家に確認することをおすすめします。
カモミールティーの腎臓への影響は?
カモミールティーの腎臓への影響は、良い面と悪い面があると言われています。カモミールティーの腎臓への影響について詳しく見ていきましょう。
【カモミールティーの腎臓に良い影響】
| 効果 |
補足事項 |
| 尿酸値を下げる |
カモミールティーに含まれるフェノリクスという成分には、尿酸値を下げる効果があると言われています。尿酸値を下げることで、痛風や腎臓病などの病気の予防や改善に役立つ可能性があります。 |
| 利尿作用がある |
利尿作用があると体内の余分な水分や老廃物を排出しやすくなります。おしっこの量を増やす作用である利尿作用は腎臓の働きも良くしてくれるため、腎臓病の予防や改善にも役立つ可能性があります。 |
カモミールティーは尿酸値を下げたり利尿作用を促したりすることで、腎臓の健康に良い効果があるとされています。
【カモミールティーの腎臓に悪い影響】
カモミールティーにはシュウ酸が含まれていると言われています。シュウ酸とは植物に多く含まれる有機酸の一種で、体内でカルシウムと結合してシュウ酸カルシウムという結晶を形成します。この結晶が腎臓にたまると、シュウ酸腎石という症状を引き起こします。
シュウ酸腎石は、激しい腰痛や血尿などの症状を伴います。また、シュウ酸腎石が詰まってしまうと腎不全や敗血症などの重篤な合併症を起こす可能性もあります。
飲み過ぎると腎臓に悪い影響を及ぼす可能性もあるカモミールティーは、適量を守って飲むことが大切です。腎臓に持病がある方や胃腸の手術を受けた方は、かかりつけの医師や管理栄養士に相談してください。
カモミールティーを飲み過ぎたらどうなる?
カモミールティーはリラックス効果や安眠効果が期待できるハーブティーですが、飲み過ぎると副作用やアレルギーのリスクが高まる可能性があると言われています。
飲み過ぎた場合に起こりうる問題について詳しくご紹介します。
【妊娠中の方は注意が必要】
先ほどお伝えしたようにカモミールティーには子宮収縮作用があるため、妊娠中の方が飲み過ぎてしまうとお腹が張るなどの副作用が起こる可能性があります。
また、定期的にカモミールティーを飲み過ぎてしまうと流産の可能性もあると言われています。妊娠中の方は、とくに飲み過ぎに注意しなければなりません。
【アレルギー反応を起こす可能性がある】
天然のキク科の植物が原料となるカモミールティーは、飲み過ぎてしまうとアレルギー症状を引き起こしてしまうことがあります。
特にキク科の花粉症やブタクサアレルギーなどを持っている方は注意が必要です。アレルギー反応には下記の症状が起こる可能性があります。
- 皮膚発疹やかゆみ
- のどの腫れや息苦しさ
- 重症化した場合にアナフィラキシーショック状態
カモミールティーを飲んだ後に体調不良を感じたら、すぐに医療機関に行きましょう。
【服用中の薬と相互作用する可能性がある】
カモミールティーには血液をサラサラにする効果があります。そのため同じような効果のある薬(抗凝固剤や抗血小板剤など)と一緒に飲むと、出血しやすくなったり薬の効果が強くなりすぎたりする可能性があります。
また、カモミールティーは肝臓で代謝されるため、肝臓で代謝される薬(抗生物質や抗不安剤など)と一緒に飲むと、薬の効果が減少したり増加したりする可能性もあります。服用中の薬がある方は、カモミールティーを飲む前に医師や薬剤師に相談しましょう。
【肝毒性の植物による悪影響が出る】
カモミールや他のハーブ類を採取するときに、誤ってピロリジジンアルカロイドを含む植物が紛れ込むことがあります。
ピロリジジンアルカロイドは肝毒性があり、長期間にわたって過剰に摂り続けると肝臓癌や肝中心静脈血栓症を起こすリスクが高くなります。とくに子供は体が小さい分危険性が高まるので、カモミールティーの飲み過ぎには注意が必要です。
カモミールティーは1日何杯まで飲める?
カモミールティーは、一日に2~4杯程度が目安といわれています。適量を守って飲むことでリラックス効果や安眠効果、生理痛の緩和などのさまざまなメリットが期待できます。
一方で、カモミールティーは飲み過ぎると副作用やアレルギーのリスクが高まる可能性があります。1日の目安量である4杯程度までなら問題ありませんが、体調によってその日に飲む量を調節すると良いですね。
また、妊娠中や子供はさまざまな影響が出やすいので、とくに適量を超えないように注意しましょう。
カモミールティーの販売店と製品
ここでは、下記4つの販売店で取り扱いのあるカモミールティーについてご紹介します。
- 無印のカモミールティー
- カルディのカモミールティー
- ルピシアのカモミールティー
- 生活の木のカモミールティー
それぞれの製品の特長についてもお伝えしていきます。
無印のカモミールティー
無印では「オーガニックハーブティー カモミール&オレンジピール」という商品が販売されています。
カモミールの香りが特長で、爽やかなオレンジピールを合わせてすっきりとした味わいに仕上がっています。
また、無印では他にも「ハーブティー ペパーミント カモミール ラズベリーリーフ」という商品もあります。リトアニア産の原料を使っており、ペパーミントのすっきりとした味わいはリフレッシュしたい時におすすめです。
無印のカモミールティーはどちらもオーガニックなので安心して飲めますよ。
カルディのカモミールティー
カルディでは「メスマー カモミールティー 25p」という商品が販売されています。青りんごのような香りのカモミールは、ヨーロッパではリラックス効果があるとされ、とくに就寝前に飲むハーブティーとして愛されてきました。
また、カルディでは「ポンパドール カモミールフラワー 10p」という商品もあります。手軽なティーバッグタイプのハーブティーで、ほのかな甘味とリンゴのような優しく暖かな香りが特徴です。
昼は気分をリラックスさせ、夜は安らかな眠りをもたらす癒しのハーブティーです。
カルディのカモミールティーはどちらも蜂蜜やレモンを加えてもおいしいですよ。
ルピシアのカモミールティー
ルピシアでは「エルダーフラワー&カモミール」という商品が販売されています。
エルダーフラワーにジャーマンカモミールをブレンドしたハーブティーで、心も体もやさしく温める爽やかな風味です。
また、ルピシアでは他にも「スウィートドリームス!」という商品もあります。カモミールにラベンダーやレモングラスなどを加えたハーブブレンドで、就寝前に飲むと安眠効果が期待できるとされています。
ルピシアのカモミールティーはどちらもオーガニックなので安心して飲めますよ。
生活の木のカモミールティー
生活の木では「有機 カモマイル・ジャーマン」という商品が販売されています。
有機栽培されたカモマイルジャーマンを使用したハーブティーで、リンゴに似た優しい香りが特徴です。温めたミルクと合わせるとよりまろやかで深みのある味がリラックスさせてくれます。
また、生活の木では「私の30日茶 おやすみ前のカモマイルブレンド」という商品もあります。カモマイルジャーマンやレモンバーム、パッションフラワーやバレリアンなど10種類のハーブを配合したハーブティーで、就寝前に飲むと安眠効果が期待できるとされています。
生活の木のカモマイルティーはどちらもオーガニックなので安心して飲めますよ。
まとめ:カモミールティーの作り方やアレンジ
この記事では、カモミールティーの作り方やアレンジ方法をご紹介しました。カモミールティーは、市販のティーバッグだけでなく、葉や生花を使っても作ることができます。葉や生花を使うと、より香りや風味が楽しめます。また、カモミールティーには、レモンやはちみつ、牛乳などを加えると、さらにおいしくなります。
カモミールティーは、リラックス効果や美肌効果など、さまざまな健康効果が期待できるハーブティーです。あなたもぜひ、カモミールティーの作り方やアレンジ方法を試してみてください。カモミールティーで、心も体も癒されることでしょう。